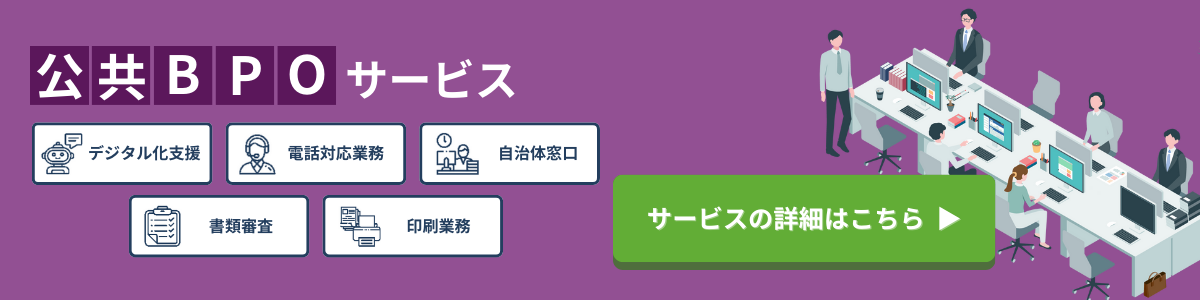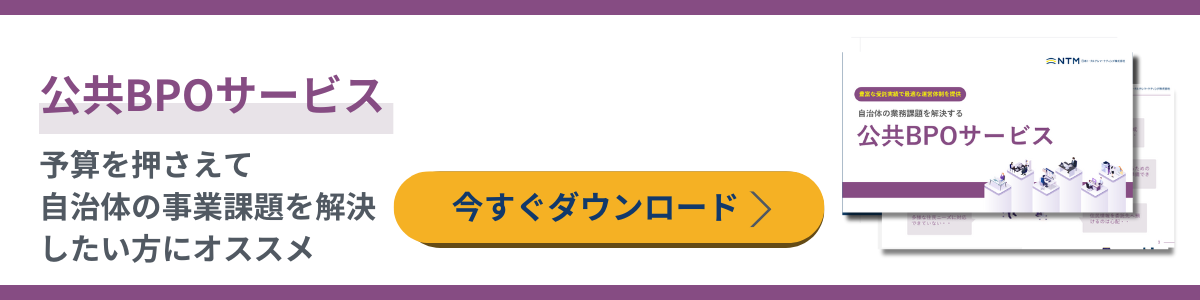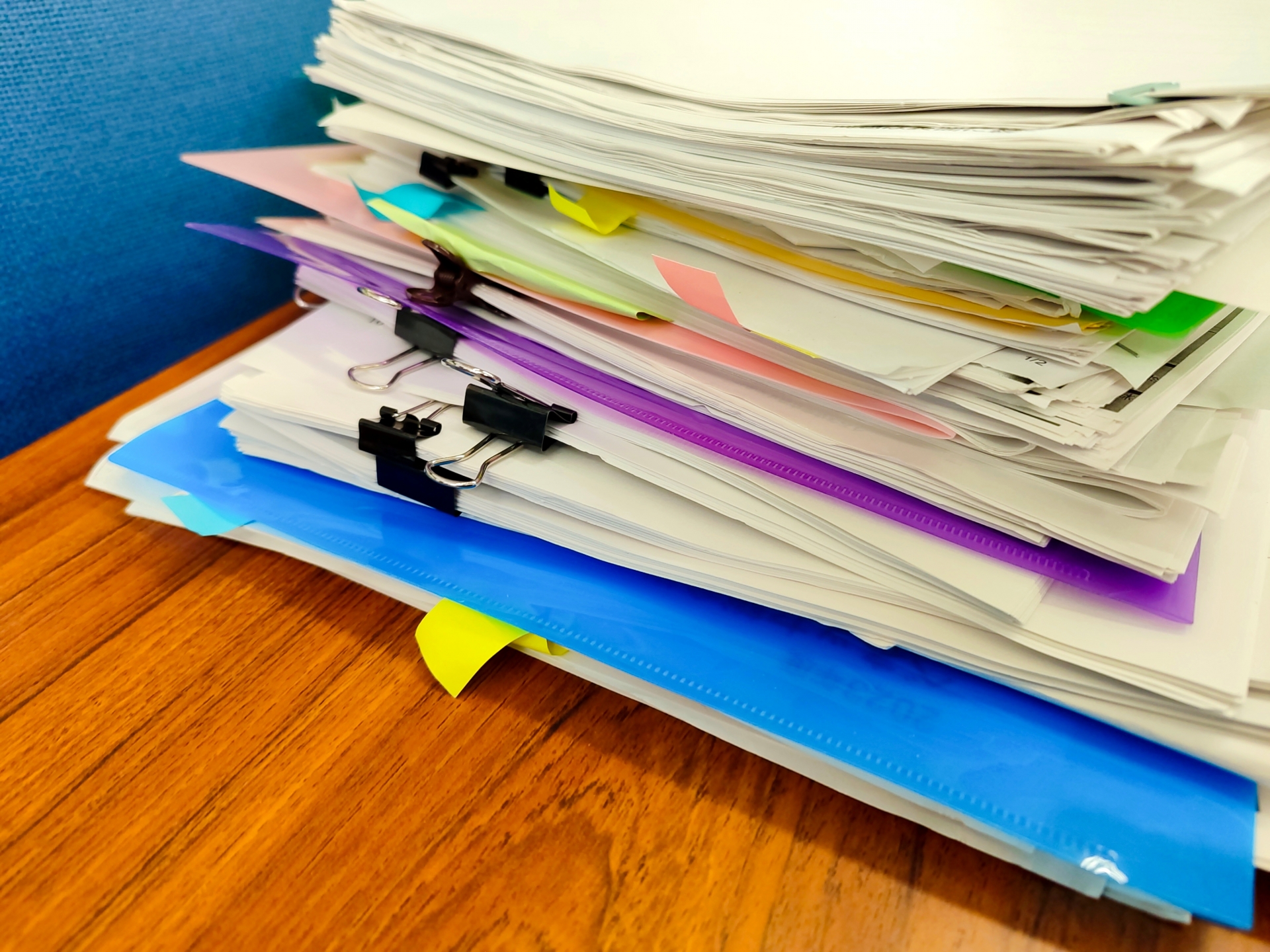地方自治体や公務員の業務効率化を進める方法は?ポイントやメリットも

地方自治体の業務は多様で煩雑化しやすい問題があります。紙ベースのアナログな作業も多く残っており、職員の負担につながっているケースも少なくありません。
職員の負担軽減や円滑な行政サービスの提供を目指すには、地方自治体と公務員の業務効率化を図ることが重要です。
今回は、地方自治体や公務員の業務効率化が必要な理由や、業務効率化が進まない背景、具体的な推進方法、取り組む際のポイントなどについて解説します。
目次
- 地方自治体や公務員の業務効率化が必要な理由
- 労働力の不足
- 多種多様な業務による負担
- 地方自治体や公務員の業務効率化に取り組むメリット
- 職員の負担軽減
- 住民サービスの向上
- 地方自治体や公務員の業務効率化が進まない背景
- アナログ業務の多さ
- ペーパーレス化の遅れ
- デジタル人材の不足
- 地方自治体や公務員の業務効率化を進める方法
- 既存業務を見直す
- 作業マニュアルを作成する
- 紙媒体の資料・文書を電子化する
- アナログ業務をデジタル化する
- RPAの活用
- AIツールを活用する
- 地方自治体や公務員の業務効率化を進める際のポイント
- ①職員とのコミュニケーションを密にとる
- ②現状の課題を洗い出す
- ③ほかの地方自治体の事例を参考にする
- 地方自治体の業務効率化は当社にご相談ください
地方自治体や公務員の業務効率化が必要な理由

地方自治体や公務員の業務効率化が必要とされる理由には、労働力の不足や幅広い業務による負担などが挙げられます。
労働力の不足
1つ目の理由は、労働力の不足です。
近年、少子高齢化による働き手の減少によって、あらゆる業界で人手不足の課題が顕在化しています。地方自治体においても例外ではなく、公務員受験者層の減少や若年層の離職増加などを背景に、慢性的な職員不足になっている地域もあります。
「自治体戦略2040構想研究会」によると、人口減少が進行するなかで、現在よりも少ない職員数で行政運営を行う必要があるとされています。
職員の負担となる長時間労働の是正や、住民への質の高い行政サービスの提供を実現するには、業務効率化によって生産性の向上を図ることが必要です。
出典:総務省「自治体戦略2040構想研究会 第一次報告」
多種多様な業務による負担
2つ目の理由には、多種多様な幅広い業務に対応することによる負担が挙げられます。
日本の地方自治体が対応する業務は、子育て・老人福祉・生活保護・学校教育・インフラ管理・都市計画など極めて幅広くなっています。海外と比べても地方自治体の対応区分は幅広く、限られた少数の職員で多種多様な業務に対応しなければなりません。
特に近年では、高齢化の進行による医療・福祉ニーズの増加や、マイナンバーカードに関する手続き・問い合わせの増加などが見られています。これにより、業務量・質ともに増大している地方自治体もあります。
公務員の働き方改革や行政サービスの利用に関する利便性の向上を図るには、業務の効率化が不可欠と考えられます。
地方自治体や公務員の業務効率化に取り組むメリット
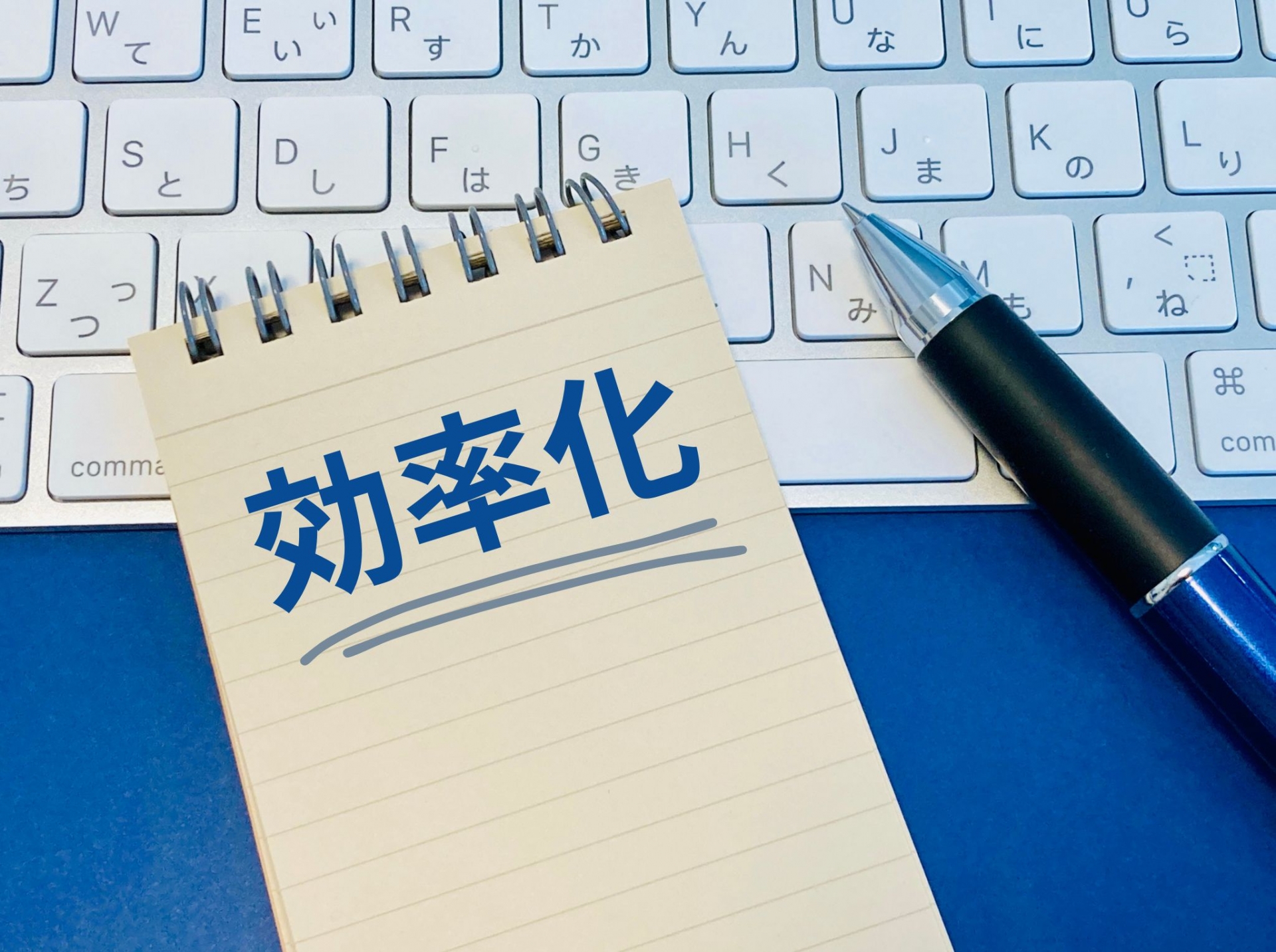
地方自治体や公務員の業務効率化に取り組むことには、職員と住民の双方にとってさまざまなメリットがあります。
職員の負担軽減
1つ目のメリットは、職員の負担軽減です。
地方自治体の業務は、窓口対応や書類整理、データ入力など多岐にわたります。なかでも繰り返しの反復作業となる書類整理やデータ入力などの業務は、労力と時間がかかりやすく職員への負担を招く大きな要因となっています。
非効率な業務を見直して作業の工数・時間を削減することにより、職員の業務負担を軽減できます。また、超過勤務の是正による労働環境の改善につながるため、職員の満足度向上や離職率の低下にも結びつくと考えられます。
住民サービスの向上
2つ目のメリットは、住民サービスの向上です。
紙ベースの事務作業や定型的な業務を見直してデジタル化・自動化を実現することにより、職員が人にしか遂行できない重要な業務に集中できるようになります。地域社会や住民にとって重要性の高い施策を積極的に推進することで、住民サービスの向上につながります。
また、窓口対応や申請・承認手続きを効率化すると、住民の待ち時間が削減されるメリットも期待されます。
地方自治体や公務員の業務効率化が進まない背景

地方自治体や公務員の業務効率化が求められているにもかかわらず、思うように推進できていない地方自治体もあります。その理由には、以下が考えられます。
アナログ業務の多さ
地方自治体の業務では、紙ベースのアナログ業務が多く存在しています。
住民が利用する各種申請書・届出書は紙で提出されるため、職員はそれらを目視でチェックして、手作業で処理・入力する必要があります。
こうした一連の作業は労力・時間がかかるだけではなく、見落としや入力ミスなどが生じやすくなり、行政サービスの信頼性を損なってしまうリスクもあります。
業務の効率化にはアナログ業務の見直しが必要ですが、「予算の確保が困難」「職員の理解が得られない」といった理由で取り組みが進まないことが考えられます。
ペーパーレス化の遅れ
民間企業ではさまざまな業種・職種でペーパーレス化が進められていますが、地方自治体では地域によって導入のばらつきがあります。
地方自治体の業務では、住民の個人情報を扱うことから、ペーパーレス化による情報セキュリティの問題が懸念されます。安全性を高めるためのシステム構築やセキュリティ管理にコストがかかるため、ペーパーレス化が進まないことがあります。
また、政府や外部の団体・機関などとの横断的な情報の共有も必要になります。ペーパーレス化によって業務フローが大きく変わるため、導入のハードルが高くなると考えられます。
このようなペーパーレス化の遅れは、業務の煩雑化を招きやすいほか、柔軟性や対応力の低下につながる可能性があります。
デジタル人材の不足
業務効率化を進めるには、システムやツールを導入・運用するための知識・スキルが求められます。しかし、地方自治体の多くは、デジタル人材の確保に課題を持っています。
ITに関する専門知識やスキルを持つ人材は民間企業に就職することもあり、地方自治体の職員や公務員として採用されるケースは多くありません。
専門知識を持つ人材がいなければ、IT技術の効果的な導入やシステムの運用・保守などができなくなり、業務の効率化を進められなくなります。
地方自治体や公務員の業務効率化を進める方法

地方自治体や公務員の業務効率化を進めるには、負担の大きい業務の見直しや、段階的なデジタル化・自動化を実施することが重要です。
ここからは、業務効率化を進める方法を解説します。
既存業務を見直す
業務の効率化を進めるには、まず既存業務の見直しが必要です。現在の業務内容とプロセスを洗い出して、無駄な作業・フローがないか確認します。
▼既存業務を見直すときに確認すること
- 複数回のやり取りが発生しているプロセスがないか
- 処理の漏れ・ミスが頻発している作業はないか
- 担当者の承認や確認のために時間のロスが発生していないか など
非効率な業務の問題点を見つけて、作業方法やフローを見直すことにより、業務効率を高められます。重要度や頻度が高い業務から取り組むことがポイントです。
作業マニュアルを作成する
職員向けに作業マニュアルを作成することも効果的です。紙をベースとしたアナログな業務では、職員が自分にとって作業しやすい方法で業務を進めている可能性があります。
作業マニュアルを作成して業務の進め方や手順を統一することで、誰もが一定の品質で業務を遂行できるようになります。これにより、非効率な業務や対応時間を削減できるほか、業務品質の向上につながります。
紙媒体の資料・文書を電子化する
紙媒体の資料や文書を電子化する方法があります。電子化して管理することで、必要な情報をすぐに検索でき、問い合わせに対する対応時間の短縮につながります。
また、物理的な保管スペースを減らせるほか、アクセス権限の設定によりセキュリティの管理も可能です。
電子化の手法には、スキャン機能が備わった複合機を利用することが一般的です。
アナログ業務をデジタル化する
アナログな業務フローをデジタル化することは、業務の効率化に大きく貢献します。
窓口業務では、紙の申請書を職員が確認して情報システムに手入力する必要がありました。手書きの文字を読み取って画像データに変換するOCRを導入することで、職員が紙帳票を手入力する必要がなくなり、入力にかかる時間の短縮につながります。
また、手入力をなくすことで処理の漏れ・ミスを防止できるほか、窓口の待ち時間を減らせるため、行政サービスの品質向上が期待されます。
ほかにも、オンラインで申請・承認を行えるワークフローシステムを導入すると、窓口業務で発生していた受付・入力・承認・書類作成などの作業を非対面で完結できます。住民はスマートフォンやタブレットで行政手続きを行えるため、来庁の手間や待ち時間の削減につながります。
RPAの活用
RPA(Robotic Process Automation)とは、PCを用いた定型的な事務作業を自動化するツールのことです。処理のルールを定義したシナリオを作成することで、データ入力や集計作業などを自動化できます。
▼RPAツールを活用できる業務の例
- 個人番号カードの交付管理
- 住民税や固定資産税などの申告書・報告書の入力
- 国民健康保険の給付申請書や異動届の入力
- 健康診断の予約入力や受診勧奨者の情報抽出 など
地方自治体では、データ入力をはじめとする定型的な作業が多く発生しやすく、業務の圧迫やヒューマンエラーにつながっています。RPAを導入して作業を自動化することで、人的リソースを有効活用できるほか、業務の正確性を担保できます。
AIツールを活用する
AI(人工知能)は、人間の知的行動をコンピュータによって代替する技術です。
AIを活用すると、手作業で対応していた転記・入力などの大量の定型業務を自動化や、データに基づく判断や分析といった高度な知的作業を代替できます。
例えば、以下のような活用法が挙げられます。
▼AIツールの活用法
- AIチャットボットによる自動応答サービス
- 議事録の自動作成
- 各種申請書の自動作成
- 保育所入所選定の自動化
- 画像・動画認識による道路管理システムの整備
- 河川水位のデータ分析による災害発生リスク予測 など
地方自治体の業務支援ツールとしてAIを導入することで、職員が人間でしか対応できない業務に注力できるようになり、現場の効率化や住民サービスの向上を図れます。
地方自治体や公務員の業務効率化を進める際のポイント

地方自治体や公務員の業務効率化を進めるにあたっては、さまざまな原因でうまく進まないことも考えられます。業務効率化の取り組みを推進するには、以下の3つのポイントを押さえておくことが重要です。
①職員とのコミュニケーションを密にとる
業務効率化の施策を検討する際は、職員とのコミュニケーションをしっかりとることがポイントです。業務フローが変わることは、これまでのアナログな作業に慣れている職員にとって不安や不満が生まれる要因となります。
職員にもメリットを感じてもらうには、密なコミュニケーションによって現場の声を収集して、現状の課題や新体制への不安などを把握することが大切です。
また、新たに業務支援ツールを導入する際は、職員への教育研修やマニュアルの作成・共有を実施して、スムーズに運用へ移行することが求められます。
②現状の課題を洗い出す
地方自治体の課題によって、業務効率化を図る適切な手段は異なります。効果を得られる施策を実行するには、現状の課題を洗い出しておくことが必要です。
業務の棚卸しを行い、『時間のかかっている作業』や『労働環境が悪化している職員』などの課題を可視化することで、効率化すべき業務やプロセスが明確になり、目的に合った手段・ツールを選定できます。
なお、業務効率化を進めるためには、目標を設定したうえで定量的・定性的な効果を測定しながら施策の改善につなげることもポイントです。
③ほかの地方自治体の事例を参考にする
ほかの地方自治体の事例を参考にすることもポイントです。多くの地方自治体では、実証実験を通じて業務効率化が進められています。しかし、施策の効果が思うように得られなかったり、ツールの導入に大きな労力がかかったりする地方自治体も見られています。
似たような課題を持つ地方自治体の成功事例・失敗事例を参考にすることで、業務効率化に関する知見やノウハウを得られます。事例を参考にする際は、実施した施策の内容だけでなく、取り組みのプロセスについても確認しておくとよいでしょう。
地方自治体の業務効率化は当社にご相談ください

少子高齢化による人口減少や医療・福祉ニーズの増加が進むなか、地方自治体には限られた人員で持続可能な行政サービスを提供し続けることが求められます。
そのためには、ペーパーレス化・電子化やAIツールの導入などにより、アナログな作業や定型作業を見直して効率化を図ることが必要です。
一方、「適切な解決策が分からない」「新たな業務プロセスへの移行方法が分からない」といった課題を持つ方も少なくありません。そのような地方自治体では、専門事業者に業務効率化のサポートを依頼することがおすすめです。
日本トータルテレマーケティングは、地方自治体向けにコールセンター運営やシステム構築業務、窓口業務、事務処理業務などをワンストップで提供しています。コールセンターAIチャットボットやマイナンバー・マイナポイントでのWEB予約システムの構築など幅広い分野で実績があり、多様なチャネルを通じた住民対応や業務委託支援を通じて、自治体における業務効率化の一助となります。