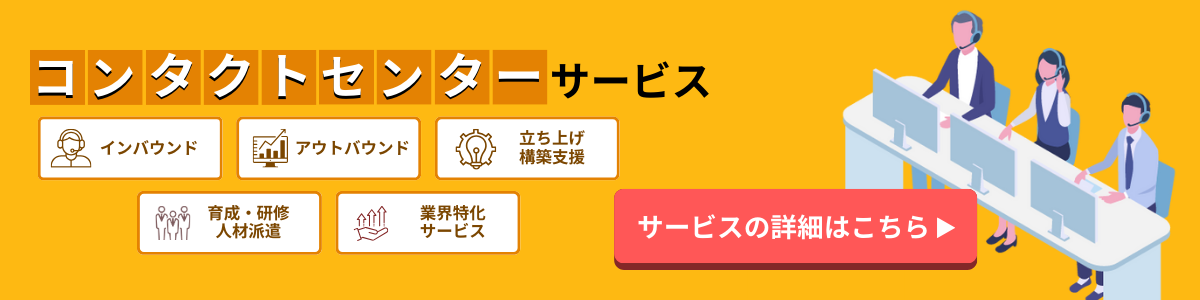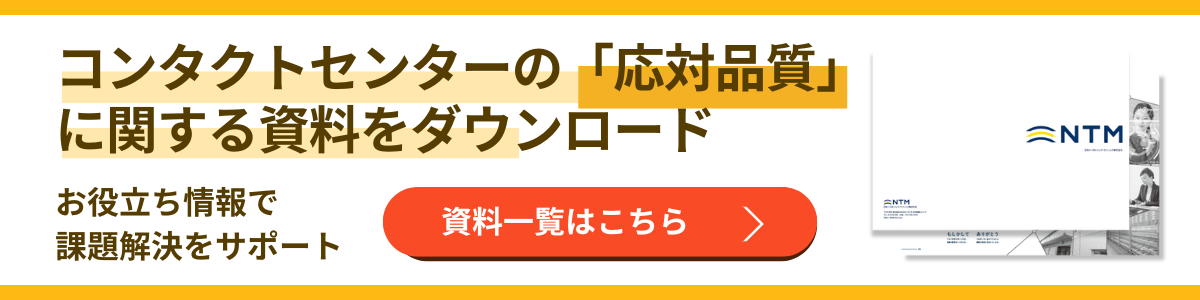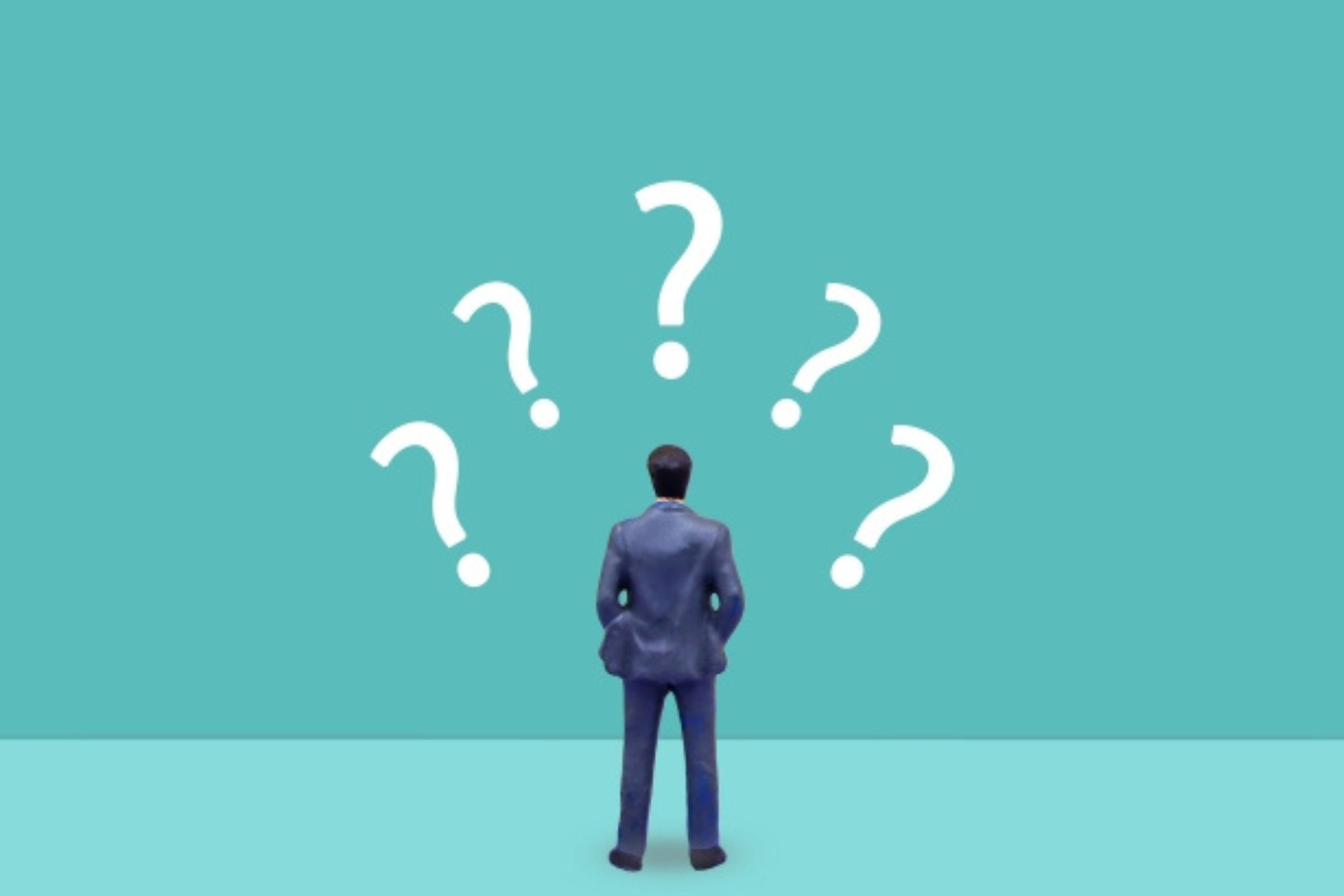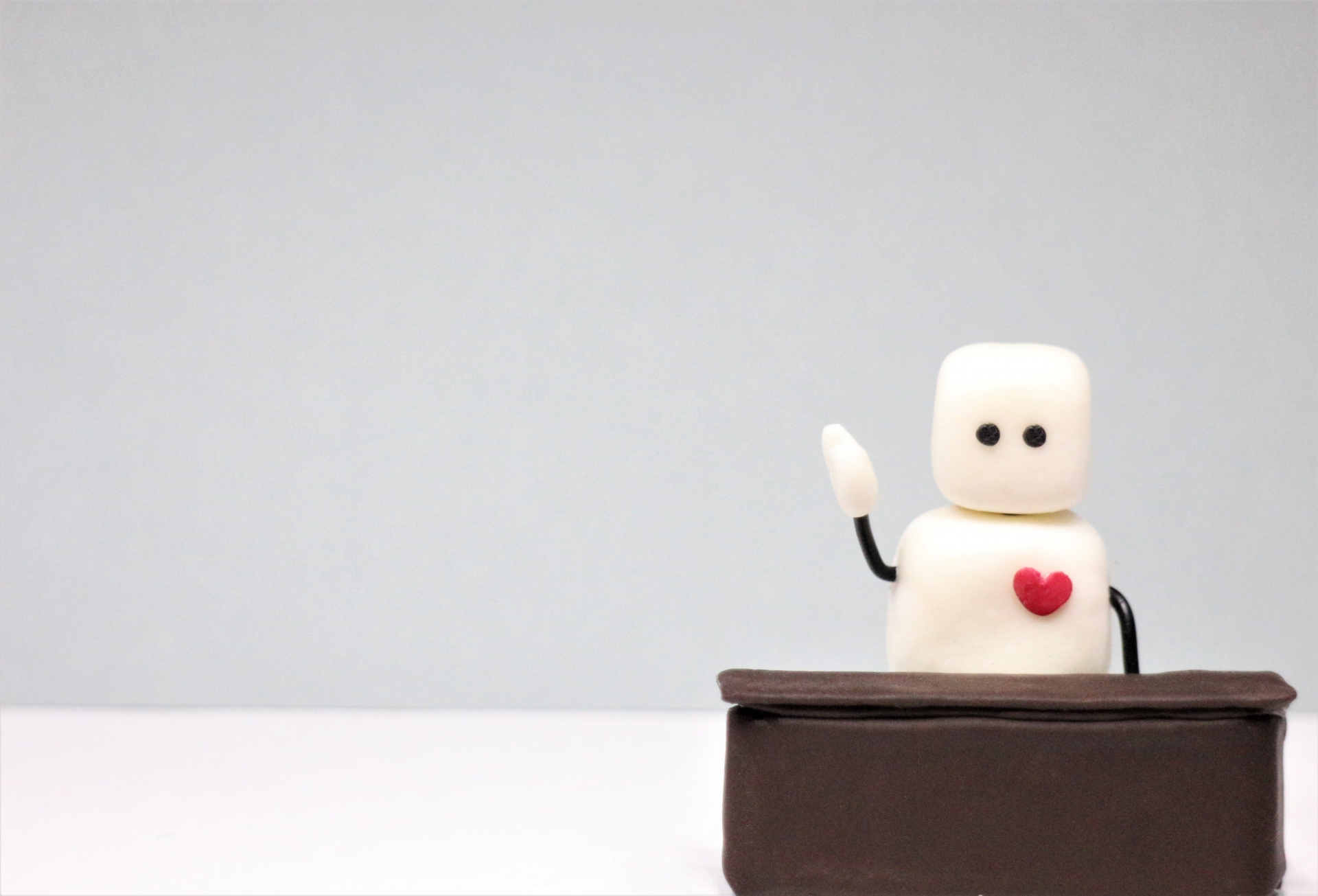コールセンターにおけるナレッジ共有の重要性と活用できるツールを解説
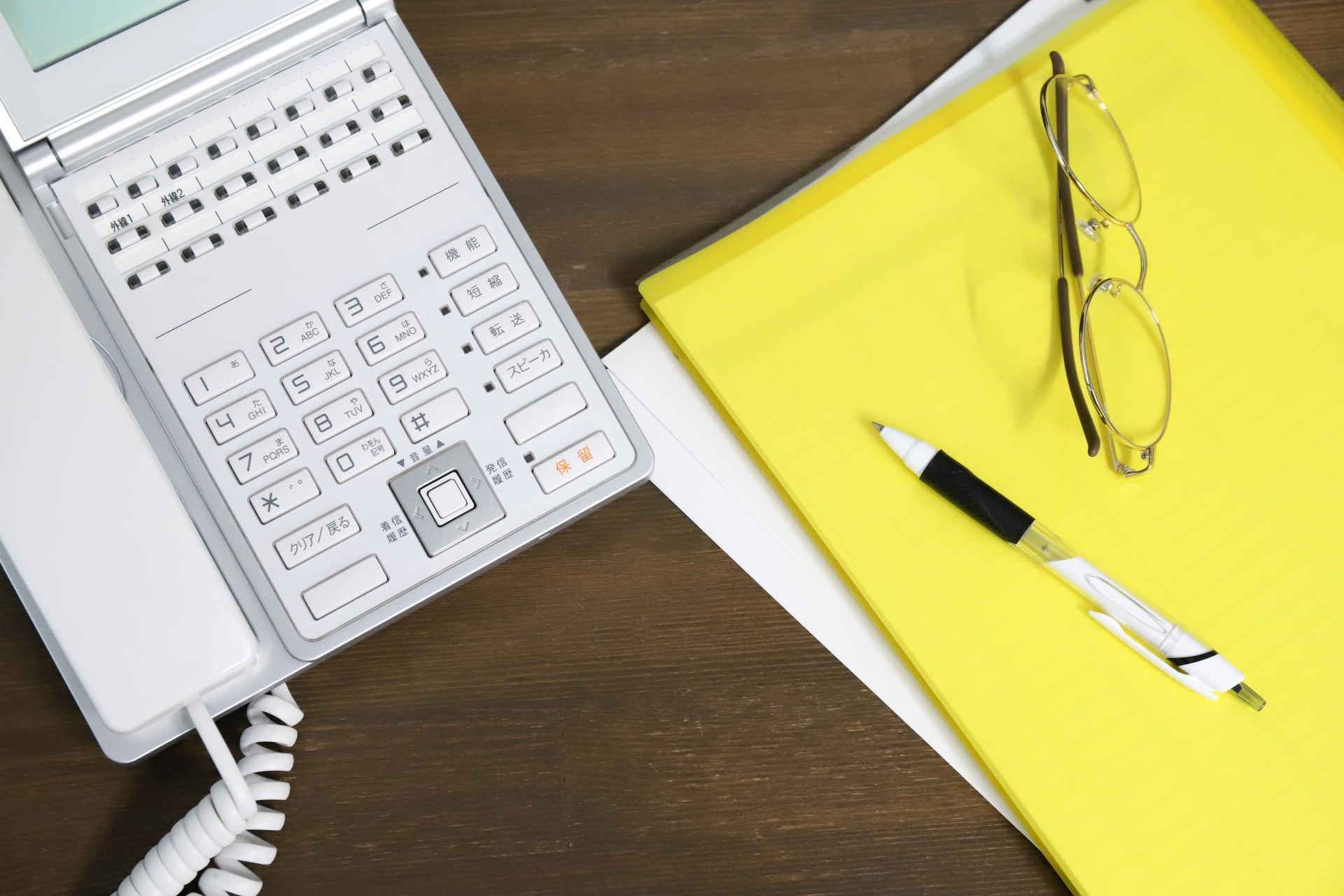
コールセンターでは、顧客から日々さまざまな問い合わせが寄せられます。
オペレーターによって知識・ノウハウに差がある場合には、応対品質や業務遂行スピードなどにばらつきが生じてしまい、顧客満足度や稼働率にも影響する可能性があります。このような問題を解決するために必要になるのが「ナレッジの共有」です。
この記事では、コールセンターにおけるナレッジ共有の重要性と期待できる効果、活用できるツールなどについて解説します。
目次
- コールセンターにおけるナレッジとは
- コールセンターにおけるナレッジ共有の重要性
- オペレーター間の知識格差を解消するため
- 応対品質の均一化を図るため
- 業務効率を向上させるため
- コールセンターにおけるナレッジ共有の効果
- 属人化の問題を解消できる
- 教育コストを削減できる
- ブランド価値を正しくアピールできる
- 柔軟な働き方が可能になる
- 応対によるストレスの軽減を図れる
- コールセンターのナレッジ共有に役立つツール
- 社内Wiki
- 文書管理システム
- オンラインストレージ
- 社内SNS
- AIナレッジツール
- コールセンターにおけるナレッジ共有のポイント
- ナレッジ共有のルールを決める
- ナレッジのアップデートを行う
- NTMが提供するナレッジツール
- まとめ
コールセンターにおけるナレッジとは

ナレッジは、「知識」や「知見」を意味する言葉です。コールセンターにおけるナレッジとは、これまでの応対によって蓄積された経験や事例などを指します。
▼コールセンターのナレッジ例
- 問い合わせや要望の内容
- オペレーターの回答・提案内容
- 各ケースの応対フロー
- トラブルやクレームを招いた事例
- 顧客満足度が高い応対の事例 など
業務マニュアルやトークスクリプトにまとめられた形式的な知識情報だけでなく、オペレーター個人が持っている暗黙的な知見・ノウハウもナレッジに当たります。
例えば、「特定のオペレーターだけが応対品質の評価が高い」という場合には、これまでの経験で培った何らかの知見を持っていると考えられます。
>>関連記事:コールセンターを自社で運営するには?起きやすい課題と対処法を解説
コールセンターにおけるナレッジ共有の重要性

コールセンターに蓄積された膨大なナレッジを組織全体で共有・活用することは、応対品質の安定化や業務の効率化を図るために重要といえます。具体的な理由には、以下が挙げられます。
オペレーター間の知識格差を解消するため
オペレーターのスキルを左右する要素の一つに知識の格差があります。
新人オペレーターよりも実務経験を積んだオペレーターのほうが、商材や顧客応対に関する深い知識を持っていると考えられます。
ナレッジを体系的に整理して社内で共有することで、経験の浅いオペレーターでも必要な情報収集と的確な対応をとれるようになり、知識格差の解消を図れます。
応対品質の均一化を図るため
コールセンターにおける課題の一つに、オペレーターごとの応対品質のばらつきがあります。
電話応対マナーへの対応や提案力、問題解決力などにばらつきがあり「オペレーターによって対応が違う」となると、顧客満足度の低下を招く可能性があります。
オペレーターの応対品質を均一化して安定した品質でサービスを提供するには、ナレッジの共有によって応対フローの標準化やスキルの平準化を図ることが重要です。
業務効率を向上させるため
オペレーターの業務効率を向上させるためにもナレッジの共有が必要です。
応対中に不明点があると、SVまたは管理者にその都度確認する必要があり、応対時間が長くなることがあります。よくある質問への回答方法や商材に関する詳細な情報などをナレッジとしてまとめることで、オペレーターが不明点を自己解決できるようになります。
スムーズかつ迅速な回答が可能になり、保留回数や応対時間を削減することは、コールセンターの生産性を向上させるためにも重要といえます。
>>関連記事:コールセンターのクレーム対応をサポートするシステムと応対のコツ!
コールセンターにおけるナレッジ共有の効果

応対履歴や問い合わせ事例などのナレッジを共有できる環境を整備することにより、コールセンターの業務や運営面でさまざまな効果を期待できます。
属人化の問題を解消できる
オペレーター個人が有していた知識・ノウハウを全体で共有することで、経験値にかかわらず誰でも一定の品質で対応できるようになります。
複雑な要望やクレーム対応など、オペレーターの勘・経験に依存していた属人的な業務を解消できると、人員配置の柔軟性が高まり社内のリソースを有効活用することが可能です。ベテランオペレーターの退職による知識・ノウハウの喪失リスクも防げます。
教育コストを削減できる
コールセンターの業務に必要なナレッジを共有・検索できる環境を整備することで、オペレーターが効率的に知識を習得できます。
新人オペレーターが短期間で着台まで移行できるようになり、教育にかかるコストの削減につながります。また、応対中にナレッジを検索できると、不明点の自己解決が可能になり、現場にいるSVや管理者がフォローする業務負担を軽減することも可能です。
ブランド価値を正しくアピールできる
商材に関するナレッジを共有することで、顧客に伝える情報や提案内容について一貫性を持たせられます。一貫性のある対応は、企業に対する信頼や安心感につながり、顧客満足度の向上に結びつきます。
また、商材・サービスの魅力や専門的な情報をわわかりやすく説明するためのナレッジを共有すると、オペレーターがブランド価値を正しくアピールでき、セールス面での訴求効果を高められます。
柔軟な働き方が可能になる
コールセンターの業務に関するナレッジを集約して、いつ・どこにいてもアクセスできる環境を整えることで、リモートワークでの働き方が可能になります。
オフィスから離れた地域に住むオペレーターのほか、育児や介護などと両立して働くオペレーターも活躍しやすい職場環境となり、人材の採用促進や定着化が期待できます。
>>関連記事:コールセンターにおけるテレワーク化の可能性と課題について解説
応対によるストレスの軽減を図れる
オペレーターの精神的なストレスを軽減する効果も期待できます。
クレーム対応や複雑な問い合わせに対するノウハウが共有されていれば、オペレーターは1人で悩むことなく過去の成功事例を参考に適切な解決策を見つけられます。
日々の業務における負荷が軽減されると、ストレスを理由とした離職の防止につながります。
コールセンターのナレッジ共有に役立つツール

ナレッジを共有する際は、膨大な情報を体系的に整理して共有・検索がしやすい形式にまとめることがポイントです。目的や用途に応じてツールを活用しましょう。
社内Wiki
社内Wikiは、従業員が自身が持つナレッジを追記・編集できるプラットフォームです。コールセンターの活用においては、主に以下のナレッジ共有に用いられます。
▼コールセンターの社内Wikiで共有すること
- マニュアルや応対手順
- 商材に関するサービス資料や価格表
- よくある質問(FAQ)のデータベース
- オペレーター個人の気づきやノウハウ など
最新バージョンの業務マニュアルや商材資料を管理・共有したり、検索機能を活用して情報収集を迅速に行ったりできます。
文書管理システム
文書管理システムは、社内で作成した文書を一元的に管理するシステムです。オペレーターが業務に活用する文書だけでなく、教育・研修で利用した資料を共有すると自己学習に活用できます。コールセンターで管理する文書には、以下が挙げられます。
▼文書管理システムで管理すること
- 製品・サービスの仕様書
- 応対フローチャート
- 各種契約書
- 教育・研修資料 など
文書のバージョン管理機能によって情報の更新履歴が明確になるため、古い情報が拡散するリスクを防ぐことが可能です。
オンラインストレージ
オンラインストレージは、文書・画像・動画などのファイルを格納してインターネット環境でアクセスできるツールです。
主にオペレーター向けのマニュアルや商材の資料などの共有に用いられます。インターネット環境でリアルタイムにデータを閲覧・編集できるため、リモートワークでのコールセンター業務に導入されています。
社内SNS
社内SNSは、従業員同士がコミュニケーションを円滑に進めるためのツールです。リアルタイムでの情報共有や意見交換、チームでの共同作業などを目的に活用されます。
▼コールセンターでの社内SNSの活用例
- キャンペーンやサービス変更の通知
- 成功事例・失敗事例の投稿
- イレギュラーな問い合わせ内容の共有
- 日々の業務や応対に関するSV・管理者によるQ&Aセッション など
気軽なコミュニケーションを通じてナレッジを投稿・共有できる環境を整えることで、オペレーターの疑問や不安の解消につながります。
AIナレッジツール
AIナレッジツールは、従来のナレッジシステムにAI(人工知能)技術を活用して、情報の蓄積・整理・検索・活用などを自動的に行うツールです。
従来のナレッジシステムでは「人が情報を整理して人が検索する」といった使い方が基本でしたが、AIナレッジツールではより効率的で精度の高い情報活用が可能になります。
▼コールセンターでのAIナレッジツールの活用例
- オペレーターが自然言語で質問を入力してAIが適切な回答を自動生成する
- オペレーターの応対中に必要な情報を画面に表示する
- 通話内容やテキスト履歴をAIが分析してナレッジに追加する
単にナレッジをデータとして蓄積するだけでなく、オペレーター対応のアシスタントや入力・検索作業の自動化による業務効率化などに活用できます。
コールセンターにおけるナレッジ共有のポイント

コールセンターでナレッジの共有を行う際は、やみくもに情報を蓄積するだけでなく、活用しやすい仕組みを整えることが重要です。
ナレッジ共有のルールを決める
ナレッジ共有のルールを明確にして運用することが必要です。定めておくルールには、以下が挙げられます。
▼ナレッジ共有のために定めるルール
- ナレッジとして扱う知識・ノウハウの内容
- ナレッジの区分・分類方法
- ナレッジの登録・更新の仕方
- バージョン管理の方法
- 各ナレッジの管理ツール など
組織全体で運用ルールを統一することで効率的なナレッジ管理が可能になります。
ナレッジのアップデートを行う
蓄積したナレッジはアップデートを行い、常に新しい情報を維持することがポイントです。
商材の変更やよくある問い合わせ傾向の変化など、常に最新の情報を反映させる必要があります。管理者が定期的な見直しと更新を行い、新旧の情報が一目でわかるように管理することで、オペレーターは常に正しい情報に基づいて応対できます。
これにより顧客への誤った案内を防ぎ、応対品質の維持につながります。
NTMが提供するナレッジツール

日本トータルテレマーケティング(NTM)のコンタクトセンターでは、カスタマーサポート業務やオペレーター研修に役立つナレッジツールを運用しています。
|
ナレッジツール |
概要 |
|---|---|
| Beauty Cosme Box(BCB) |
|
| eラーニングシステム |
|
| QA ナレッジ |
|
これらのツールを活用することで、オペレーターが効率よく知識を習得し、標準化された高品質なサービスを提供できます。
まとめ

コールセンターで質の高い応対を維持するには、ナレッジ共有が不可欠です。ノウハウや応対スキルを全体で共有することで属人化を防ぎ、品質の均一化や顧客満足度の向上につながります。
NTMでは「品質管理部」を設置し、ナレッジ共有の仕組みを整えることで標準化されたカスタマーサービスを提供しています。