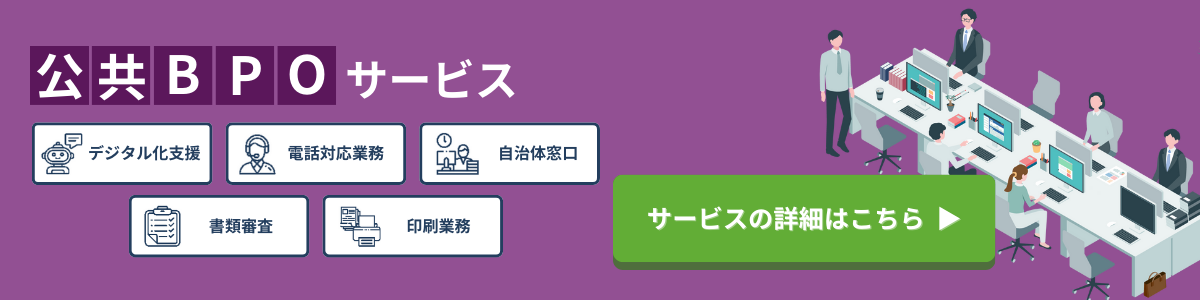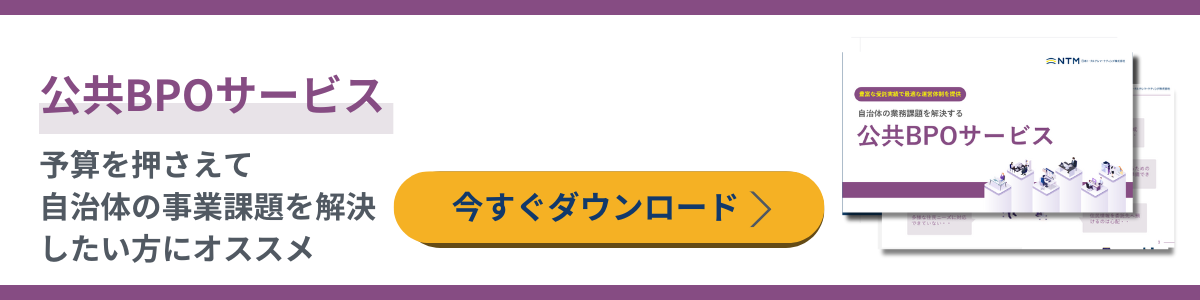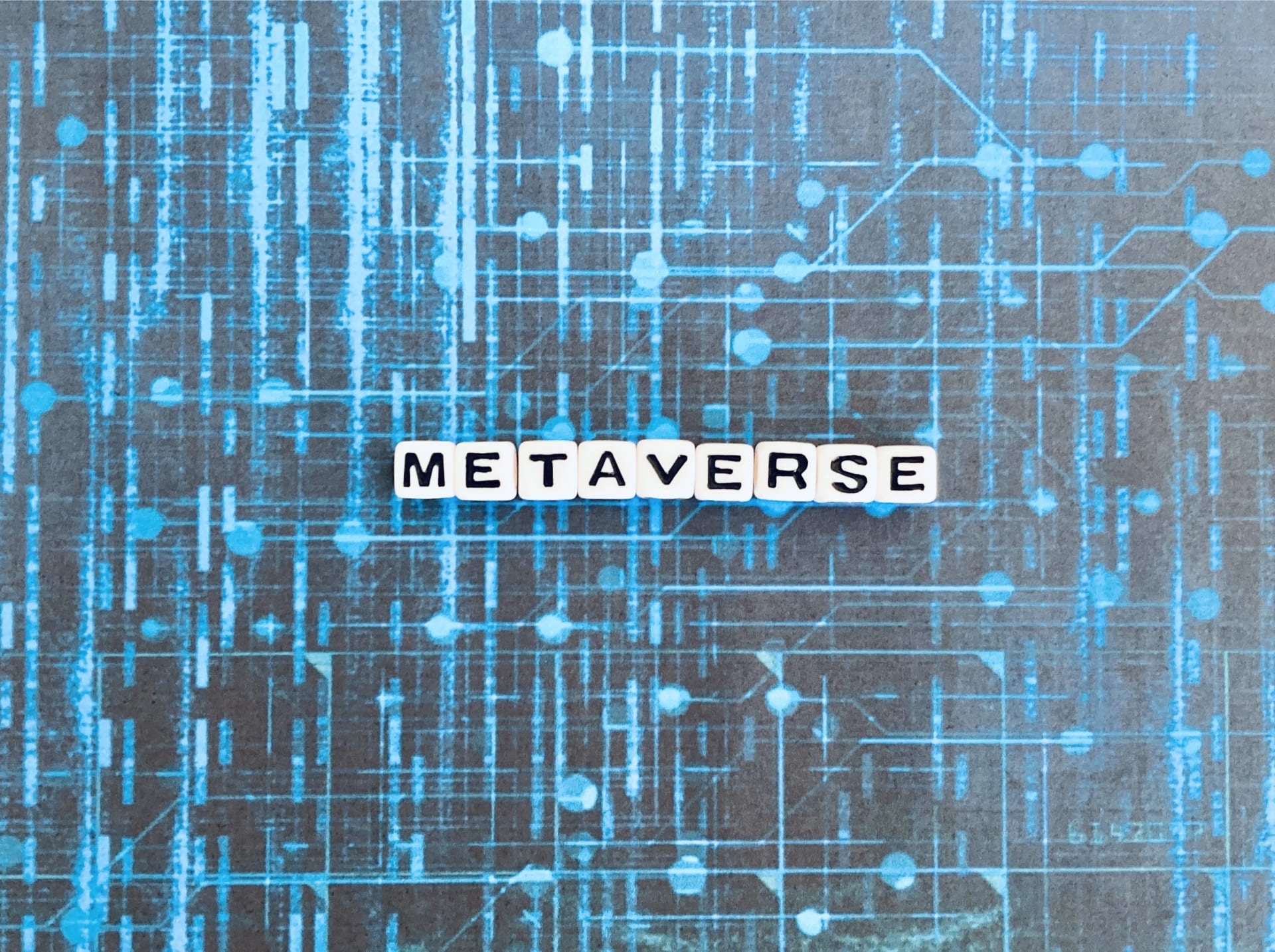特命随意契約とは?契約が認められるケースと必要になる書類を解説

随意契約の1種である特命随意契約は、どのようなケースでも認められるものではなく、契約を締結できるケースは限られています。
そこで今回は、特命随意契約の概要や認められるケース、契約締結のために必要な書類をご紹介します。
目次
特命随意契約とは 随意契約の種類

随意契約とは、競争入札なしに事業者と契約を締結する方法です。随意契約には特命随意契約(特命随契)、少額随意契約(少額随契)、不落随意契約(不落随契)の3種類があり、単に随意契約という場合は特命随意契約を指すことが一般的です。
特命随意契約は、国や自治体が公共工事を発注する際に競争入札をせず、事業者と契約を締結できますが、法令で定められた要件を満たす必要があります。
随意契約の種類
・特命随意契約(特命随契)
・少額随意契約(少額随契)
・不落随意契約(不落随契)
少額随意契約と不落随意契約

前述の通り、随意契約には特命随意契約以外に少額随意契約と不落随意契約があります。
ここでは、それぞれの随意契約の概要を紹介しながら、特命随意契約との違いを解説します。
少額随意契約
少額随意契約とは、予定価格が少額である際に2社以上の企業から見積もりを取り、見積もり内容を比較して契約相手を決める形式のことです。
特命随意契約との違いは、複数の事業者に見積もりを取る(あいみつをする)かどうかです。特命随意契約では、競争入札を行わず特定の事業者と契約するため、見積もりは1社のみです。一方、少額随意契約では、少なくとも2社以上から見積もりを取ります。
不落随意契約
不落随意契約とは、競争入札の入札者がいなかった、落札されなかった落札したが契約しなかったなどによって、再び競争入札をする時間的猶予がない際に結ばれる契約です。このような場合には、あらかじめ定められた最低価格や条件にもとづき契約が行われます
下記の理由で落札者が決まらなかった場合に、随意契約で契約を締結する方法を不落随意契約といいます。
・競争入札に参加する入札者がいなかった場合
・入札不落などで落札者が決定しなかった場合
・落札したが落札者が契約を辞退し契約しなかった場合
特命随意契約との違いは、競争入札をするかどうかです。前述の通り、特命随意契約は競争入札を実施しませんが、不落随意契約は競争入札を実施します。
特命随意契約が認められるケース

前述の通り、特命随意契約は自由に行えるものではなく、法令で定められた要件を満たす必要があります。
地方公共団体が発注する場合は「地方自治法施行令」、国が発注する場合は「予算決算及び会計令」が適用されます。
いずれも長文のため、冒頭のみを取り上げて紹介します。
|
地方自治法施行令167条の2 地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。 2 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 (以下省略) 引用:e-Gov 法令検索|地方自治法施行令 |
|---|
|
予算決算及び会計令 第99条 会計法第29条の3第5項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 国の行為を秘密にする必要があるとき。 2 予定価格が四百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 3 予定価格が三百万円を超えない財産を買い入れるとき。 4 予定賃借料の年額又は総額が百五十万円を超えない物件を借り入れるとき。 5 予定価格が百万円を超えない財産を売り払うとき。 (以下省略) 引用:e-Gov 法令検索|予算決算及び会計令 |
|---|
以下では、地方自治法施行令167条の2にある特命随意契約が認められる条件の一部を取り上げて解説します。
契約の性質または目的が競争入札に適さない場合
地方自治法施行令167条の2第2号では、「性質又は目的が競争入札に適しない」(地方自治法施行令167条の2第2号)契約する場合に特命随意契約を認めています。
判断基準としては、具体的には、次のようなケースが該当します。
・特定のものでなければ役務を提供できない場合
例:特殊な技術を用いる場合や特定の業者でなければ対応できない場合など
・額面価格が定められているものなど、競争性がないと認められる場合
例:切手や新聞の購入など入札の必要がないもの
特定の施設などから物品を買い入れまたは役務の提供を受ける契約をする場合
地方自治法施行令167条の2第3号では、特定の施設から物品を「買い入れる契約」、または「役務の提供を受ける契約」(地方自治法施行令167条の2第3号)などに該当する場合は特命随意契約が認めています。
具体的には、次のようなケースが該当します。
・特定の施設などから物品を「買い入れる契約」の例:
障害者への職業訓練施設で作成、製作された物品を購入するケース
・「役務の提供を受ける契約」の例:
高齢者や母子家庭を支援する団体から、役務の提供を受けるケース
新規事業分野のベンチャー・スタートアップから新商品を買い入れる契約をする場合
地方自治法施行令167条の2第4号では、以下の場合に特命随意契約を認めています。
「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続きにより、買い入れる契約をするとき。」(地方自治法施行令167の2第4号)
ここでいう「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」(地方自治法施行令167条の2第4号)とはベンチャー企業やスタートアップを指します。そして、「新商品として生産する物品」とは、納品物に新規性があることを指します。
つまり、ベンチャー企業やスタートアップ企業から納品物に新規性があり他企業の納品物よりも優れた機能性がある場合は特命随意契約を認めています。
緊急の必要により競争入札ができない場合
地方自治法施行令167条の2第5号では、以下の場合に特命随意契約を認めています。
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」(地方自治法施行令167条の2第5号)
具体的には、次のようなケースが該当します。
・災害時
・早期に契約が必要なケース
日本は地震の発生が多い地震大国として知られています。地震によって堤防や道路の崩壊・地すべりなどの災害が起きた際、物資の購入や機材の借り入れ、重要設備の故障修理は速やかに進める必要があるため、特命随意契約が認められます。
競争入札に付することが不利な場合
地方自治法施行令167条の2第6号では、「競争入札に付することが不利と認められるとき」(地方自治法施行令167条の2第6号)に特命随意契約を認めています。
具体的には、次のようなケースが該当します。
・工事や事業の途中で新たに競争入札を行うと、事業自体の完了が困難になるケース
・契約手続きが長引くことで、事業の遅れや価格の高騰など、財政に影響が出るおそれがあるケース
相場より著しく有利な価格で契約ができる場合
地方自治法施行令167条の2第7号では、「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき」(地方自治法施行令167条の2第7号)に特命随意契約を認めています。
具体的には、次のようなケースが該当します。
・提供される物品の品質や性能に問題がなく、他と比べても劣っていないケースで、
・時価を基にした予定価格や競争入札よりも明らかに有利な価格で契約できるケース
特命随意契約のメリット

特命随意契約には以下のようなメリットがあります。
・競争入札を行わないため、迅速に契約を締結できる
・発注先に選ばれると、確実に契約を締結できる
競争入札をする場合、契約締結までに時間を要します。一方で、特命随意契約は競争入札をせず、はじめから1社に絞って契約を進めるため、迅速に契約を締結できて入札にかかる時間や労力などのコストを抑えられます。
特命随意契約のデメリット
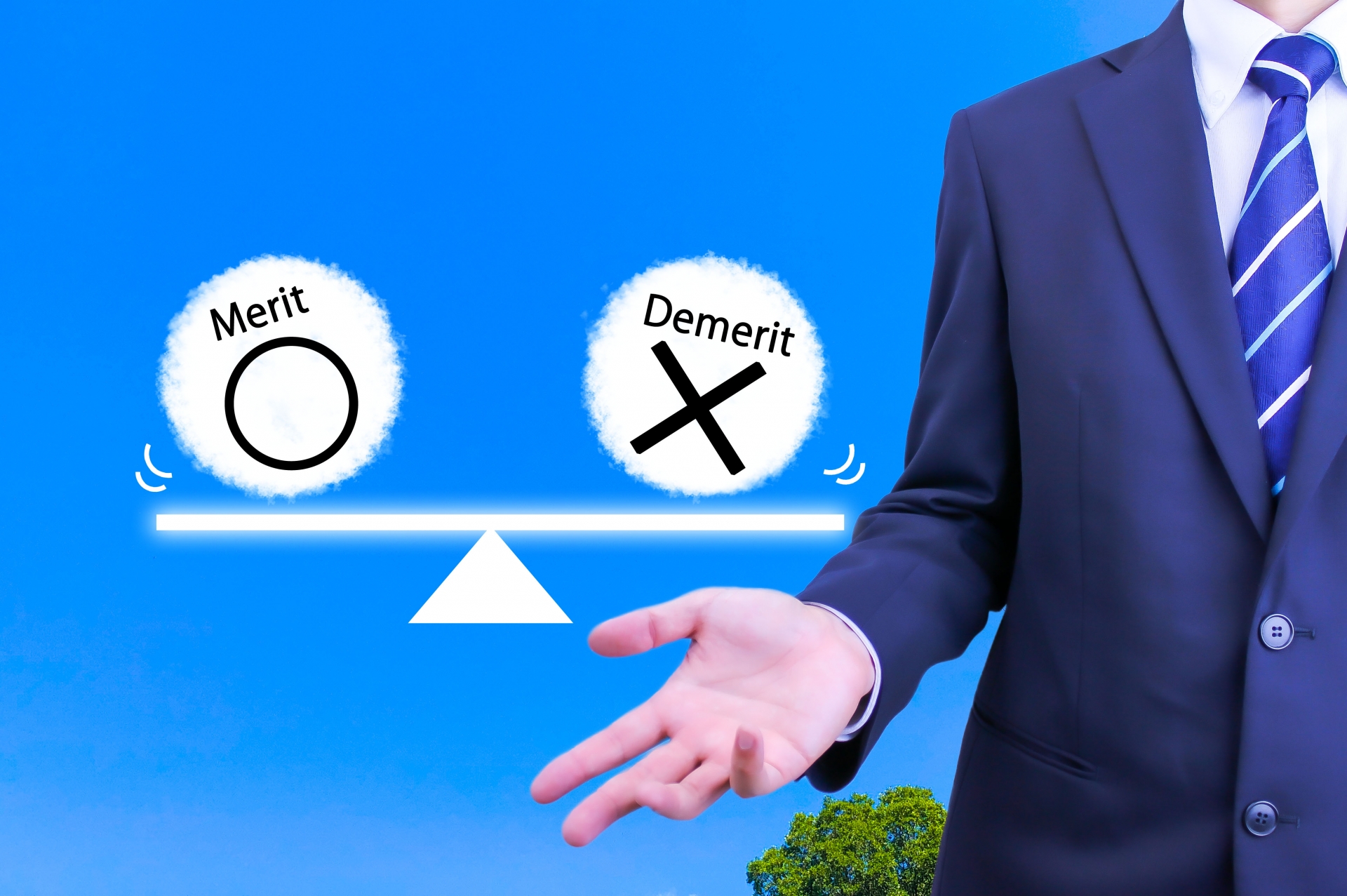
特命随意契約は迅速に契約を締結できるため、入札にかかる時間や労力などのコストを抑えられる一方で、以下のようなデメリットもあります。
・特命随意契約を行うには、前述の条件を満たす必要がある
・通常の入札で実績を積み重ねていない場合、発注先に選ばれるのは難しい
特命随意契約は、双方の合意だけで進められるものではなく、所定の条件を満たさなければ認められません。検討する際は、この点を理解しておく必要があります。
随意契約理由書について

特命随意契約を締結する際には、「随意契約理由書」を作成しなければなりません。理由書には「機種選定理由書」、「業者選定理由書」、および両方をまとめた「選定理由書」の3種類があります。
随意契約理由書の種類
・機種選定理由書
・業者選定理由書
・選定理由書
以降でそれぞれ順に紹介します。
機種選定理由書
物品を競争性のない特命随意契約で購入した場合に作成する書類です。主に以下の3点について記載します。
- 使用目的:なぜ購入しなければならないのか、理由を簡潔に記載する
- 求められる性能や条件:事業や工事達成のために必要な性能について、根拠を含めて記載する
- 選定理由:選定した物品が、事業や工事に求められる性能に合致すると判断した根拠を記載する。複数の物品から選定したケースでは、カタログから数値を転記した「性能比較表」を付けることもある
機種選定理由書の記載一例
・購入目的:購入目的を簡潔に記載
・必要条件:最低限必要な機能を検討し、リストアップ
・選定理由:選定した物品が事業や工事に必要な性能を満たす根拠を記載。
複数の物品から選んだ場合は、カタログの数値を使った性能比較表を添付する場合あり
業者選定理由書
競争なしにその業者を選んだ理由について記載する書類です。
たとえば、特殊な技術や部品が必要で、その業者しか取り扱いがなかったケースでは、その旨を記載します。
公共BPOは当社へご相談ください

当社では、コンタクトセンターやフルフィルメントなど幅広い業務の受託実績がございます。多様な業務支援の実績を活かし、公共BPOに関するご相談にも柔軟に対応いたします。ぜひお気軽にご連絡ください。