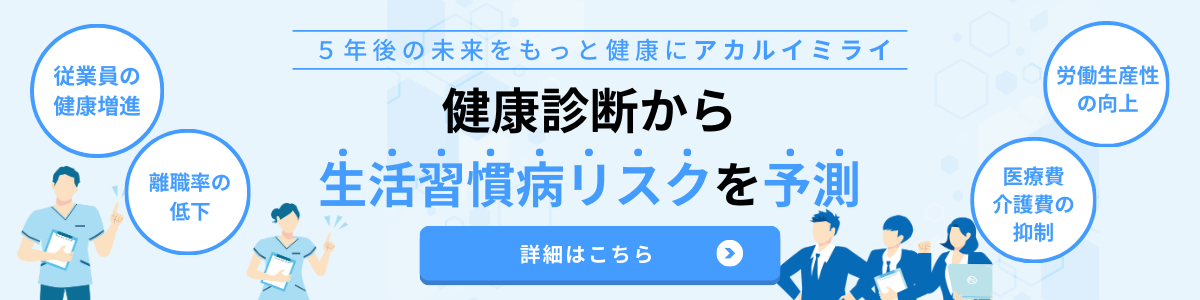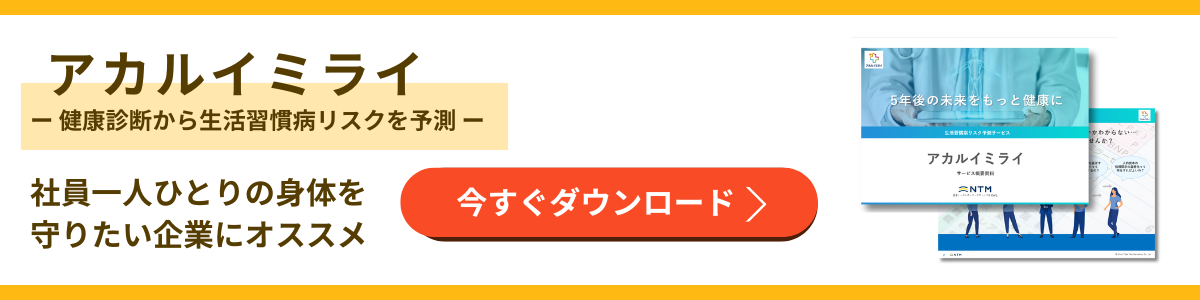エイジフレンドリーとは?取り組むためのポイントや補助金制度を解説します!

少子高齢化が進む日本社会において、高齢者も安心して働ける職場環境づくりが求められています。そこで注目されているのが「エイジフレンドリー」という考え方です。
ここでは、「エイジフレンドリー」とはどのようなものなのか、概要や取り組むためのポイント、補助金制度などについて解説します。
目次
- エイジフレンドリーとは?
- エイジフレンドリーが求められている背景は?
- 人手不足
- 高齢者の労働人口増加
- 高齢就業者の労働災害増加
- エイジフレンドリーに取り組むためのポイント
- 安全衛生管理体制を確立する
- 職場環境を改善する
- 安全衛生教育の実施
- 高年齢労働者の健康や体力を把握
- 健康管理・運動習慣の推進
- エイジフレンドリーの実現に必要なことは?
- 多様な働き方を推進する
- 従業員同士のコミュニケーションを促進する
- メンタルヘルスに関する研修を行う
- ストレスチェックを定期的に行う
- エイジフレンドリー補助金とは?
- エイジフレンドリー補助金のコースは?
- 総合対策コース
- 職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)
- 転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース
- コラボヘルスコース
- 従業員の健康意識向上は当社にご相談ください
エイジフレンドリーとは?
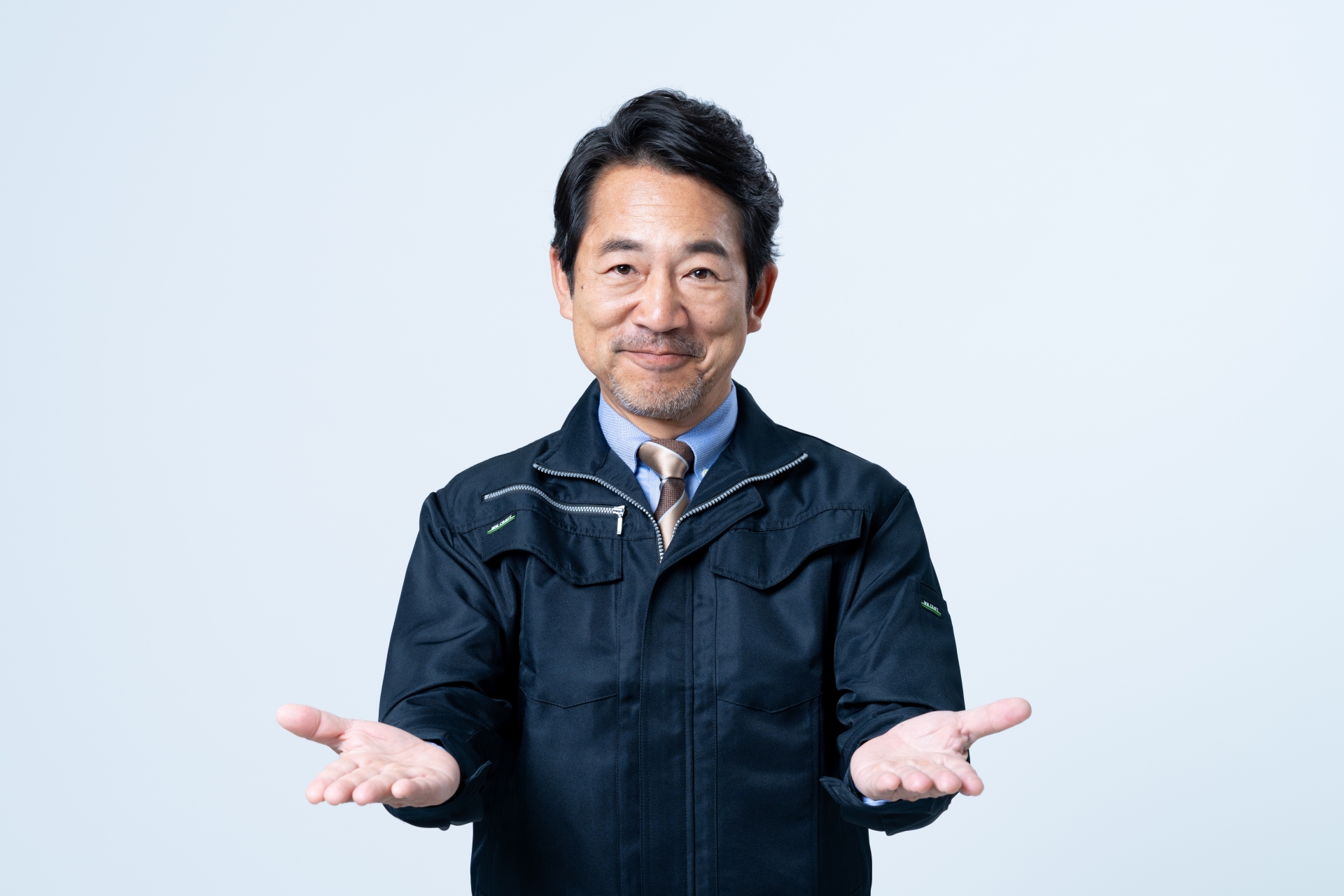
エイジフレンドリーとは、高齢者の身体的・心理的な特性を考慮し、誰もが年齢に関係なく安心して働ける安全で健康的な職場環境を指す言葉です。WHO(世界保健機関)や欧米の労働安全衛生機関によって提唱されており、日本でも高齢社会への対応策として注目されています。
転倒防止のための職場整備や、視覚・聴覚への配慮、柔軟な勤務形態の導入などがその一例です。エイジフレンドリーな取り組みは、高年齢労働者だけでなくすべての従業員にとって働きやすい環境の実現にもつながるでしょう。
エイジフレンドリーが求められている背景は?
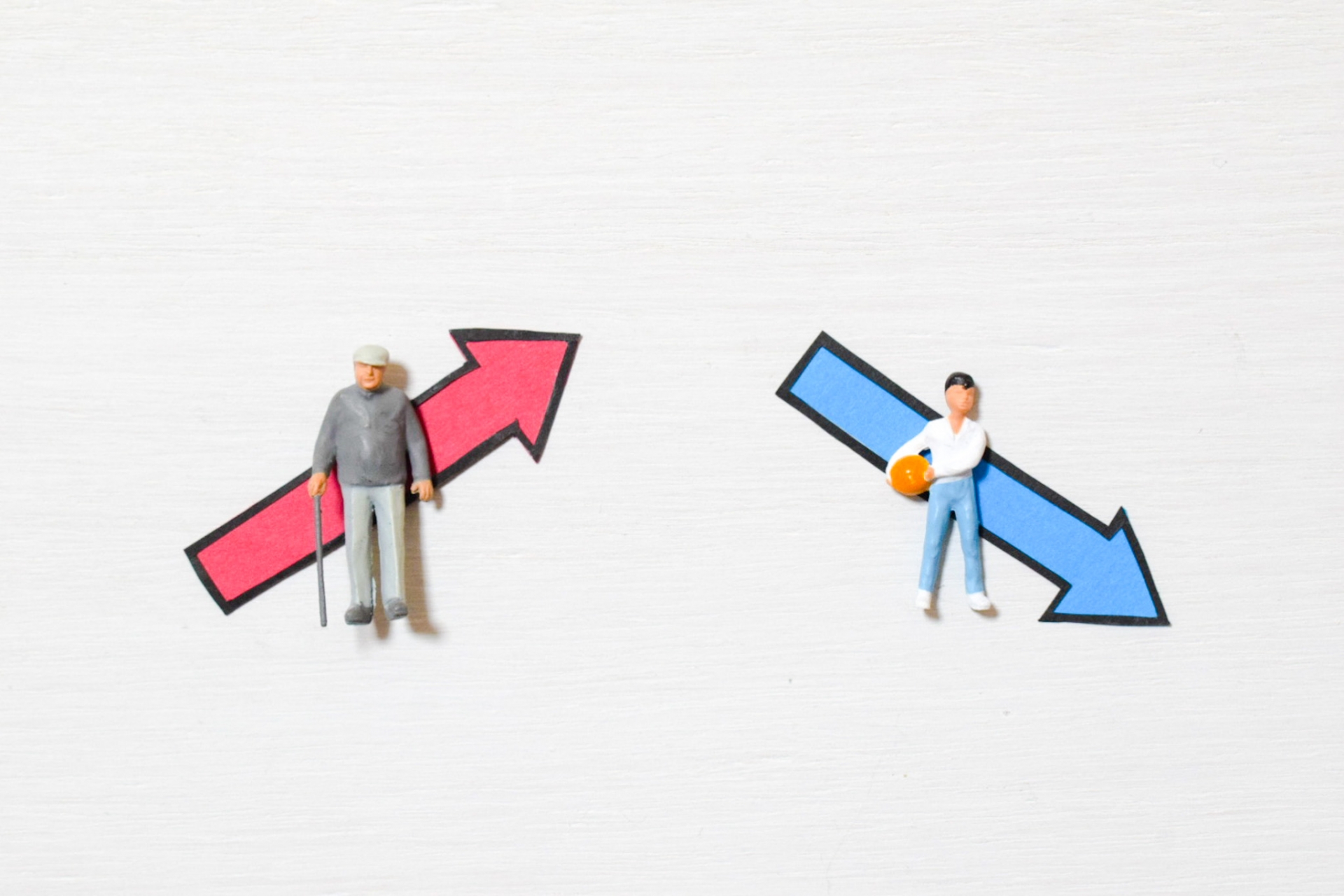
日本では少子高齢化が進行しており、企業の人手不足が深刻な課題です。エイジフレンドリーは社会的要請に応える考え方であり、高齢者を含めた多様な人材が活躍できる環境の整備が求められています。
ここでは、エイジフレンドリーが求められる背景について紹介します。
人手不足
日本の労働市場では、少子高齢化の影響によって労働人口の減少が深刻化しています。若年層の人口が減り続ける一方で、企業は持続的な成長を目指す上で、多様な人材の確保が急務です。そのため、年齢を問わず誰もが働きやすい職場環境を整備する必要があります。
この取り組みは、高齢者の特性を理解し、安全かつ健康に働ける場を提供する取り組みです。このような配慮があることで、高齢者だけでなく、女性や障がいのある方など、多様な人材が能力を発揮しやすくなるでしょう。人手不足への対応策として、エイジフレンドリーな職場づくりは今後ますます重要です。
高齢者の労働人口増加
近年の日本では、65歳以上の労働者が増加し、定年後も働き続ける高齢者の就業率が上昇しています。このような動きは、年金制度や生活費の問題に加え、社会参加への意欲の高まりなどが背景にあります。
しかし、体力や身体的機能が低下することもある高年齢労働者にとって、従来の職場環境では負担となる場面も少なくありません。エイジフレンドリーは、高齢者や女性が安心して働き続けられるように、作業負担の軽減や設備の見直しなどを意味します。企業には、働く人の年齢や状態に応じた柔軟な対応がますます求められています。
高齢就業者の労働災害増加
高齢就業者の増加にともない、労働災害の件数における高齢者の割合も年々上昇しています。特に60歳以上の死傷者数は顕著で、身体機能や反応速度の低下によって、小さな段差や滑りやすい床などでも重大な事故につながる危険があります。高齢者は若年層と比べて回復にも時間がかかるため、予防が重要です。
エイジフレンドリーは、このようなリスクに対応するための考え方であり、労働災害の防止を目的に職場環境の整備促進が求められます。事故を未然に防ぎ、高齢者が安心して働ける環境づくりは、企業の責任でもあり、持続可能な雇用が実現できるでしょう。
エイジフレンドリーに取り組むためのポイント

高齢化が進む中で、企業が年齢を問わずすべての従業員にとって健康的で柔軟性のある職場環境を整備することは、ますます重要視されています。
ここでは、企業がエイジフレンドリーに取り組む際のポイントを解説します。ポイントを押さえることで、従業員の働きやすさと生産性の向上につながるでしょう。
安全衛生管理体制を確立する
安全衛生管理体制とは、労働者を労働災害から守るために構築される体制であり、特に高年齢労働者が安心して働ける環境づくりに欠かせません。経営トップが方針を明確にすることで現場の意識が高まり、安全対策もより強化されます。
エイジフレンドリーとは、このような体制整備によって年齢問わず働きやすい職場を実現する取り組みでもあります。継続的な点検と改善によって、労働災害のリスクを抑え、従業員が安心して働けるようになるでしょう。
職場環境を改善する
高年齢労働者の増加にともない、企業は彼らの身体的変化に配慮した職場環境の整備が求められています。視力の低下に対応した照明の明るさ調整や、段差の解消、滑りにくい床材への変更などが効果的です。
特に現場作業の多い職種では、細やかな配慮が大きな事故の防止につながります。日常業務に即した改善の積み重ねが、エイジフレンドリーな職場づくりには不可欠です。
安全衛生教育の実施
労働安全衛生法では、事業者から労働者に対する安全衛生教育の実施が義務付けられています。特に高年齢労働者に対しては、反応や理解のスピードに配慮し、時間をかけた丁寧な教育が必要です。
現場の危険箇所を具体的に示し、視覚や聴覚の変化に配慮した教材を使うことで、効果的な教育が可能になります。こうした取り組みがエイジフレンドリーの考え方に基づくものであり、個々に寄り添う教育は意欲や安全意識の向上にもつながります。
高年齢労働者の健康や体力を把握
高年齢労働者を雇用する際には、加齢によって体力や身体機能に変化が生じることを理解し、健康や体力の状況を定期的に把握する体制が重要です。健康診断の実施や簡易的な体力チェックによって個人の状態を可視化し、無理のない業務配分やリスクの予防につなげられます。
従業員一人ひとりの特性に応じた対応を通じて、安心で安全な職場が実現するでしょう。
健康管理・運動習慣の推進
高年齢労働者が安全かつ健康的に働き続けるためには、日常的な健康管理と運動習慣の推進が不可欠です。
企業には、従業員が自身の体調や身体機能を正しく把握し、生活習慣の改善や体力維持に前向きに取り組めるよう支援する環境づくりが求められます。ストレッチや健康プログラムの導入は、労働災害の予防にも有効です。
エイジフレンドリーの実現に必要なことは?

エイジフレンドリーには、安全対策や健康管理に加えて、働き方や職場環境の工夫も欠かせません。企業が柔軟な制度を整えることで、高年齢労働者も自分らしく働き続けられる環境が実現します。
ここでは、エイジフレンドリーな職場の実現に必要な取り組みについて紹介します。
多様な働き方を推進する
年齢に関係なく誰もが健康で働ける職場づくりを目指すエイジフレンドリーの理念を実現するためには多様な働き方の導入が有効です。たとえば、短時間勤務や週休3日制、時差出勤、1時間単位での有休取得などが挙げられます。
高年齢労働者には、体調の波や通院などの事情を抱える人も少なくありません。そのため、個々の状況に応じて働き方を選べる制度は、労働者の大きなメリットといえます。柔軟な労働形態を整えることで、高齢者の職場定着率向上にもつながるでしょう。
従業員同士のコミュニケーションを促進する
良好な人間関係と円滑な情報共有は、エイジフレンドリーな職場を築く上で不可欠です。特に年齢や立場の異なる従業員が協力して働くためには、日頃からコミュニケーションの土台づくりが重要となるでしょう。世代間のギャップを感じさせない風通しのよい職場では、高齢者も気後れすることなく意見交換に加われます。
また、従業員同士の信頼関係が深まることで、業務上の連携や役割分担がスムーズに進み、職場全体の生産性や満足度の向上にも寄与するでしょう。
メンタルヘルスに関する研修を行う
心の健康は働き続ける上で欠かせない要素であり、エイジフレンドリーな環境づくりにも直結します。企業がメンタルヘルスに関する研修を実施する目的は、従業員に正しい知識と対処法を身につけてもらい、健全な職場環境を維持することです。
特に高年齢労働者は、体力的な不安や職場での孤立感から精神的負担を感じることもあるでしょう。放置すれば、うつ病や適応障害などの深刻な問題に発展するおそれもあるため、早期の気づきとケアの仕組みが求められます。
ストレスチェックを定期的に行う
高年齢労働者の心身両面に配慮した職場づくりも、まさにエイジフレンドリーの方針に沿うものです。その一環として、定期的なストレスチェックの実施が挙げられます。加齢によって作業能力が低下したり、世代間ギャップによる人間関係の悩みが生じたりと、高齢者が抱えるストレスは多岐にわたります。
ストレスチェックの実施によって、客観的に状態を把握し、問題の早期発見と対策が可能になります。こうした取り組みが、従業員の安心感や定着率の向上にもつながるでしょう。
>>資料:(無料)アカルイミライに関するサービス資料はこちら
エイジフレンドリー補助金とは?
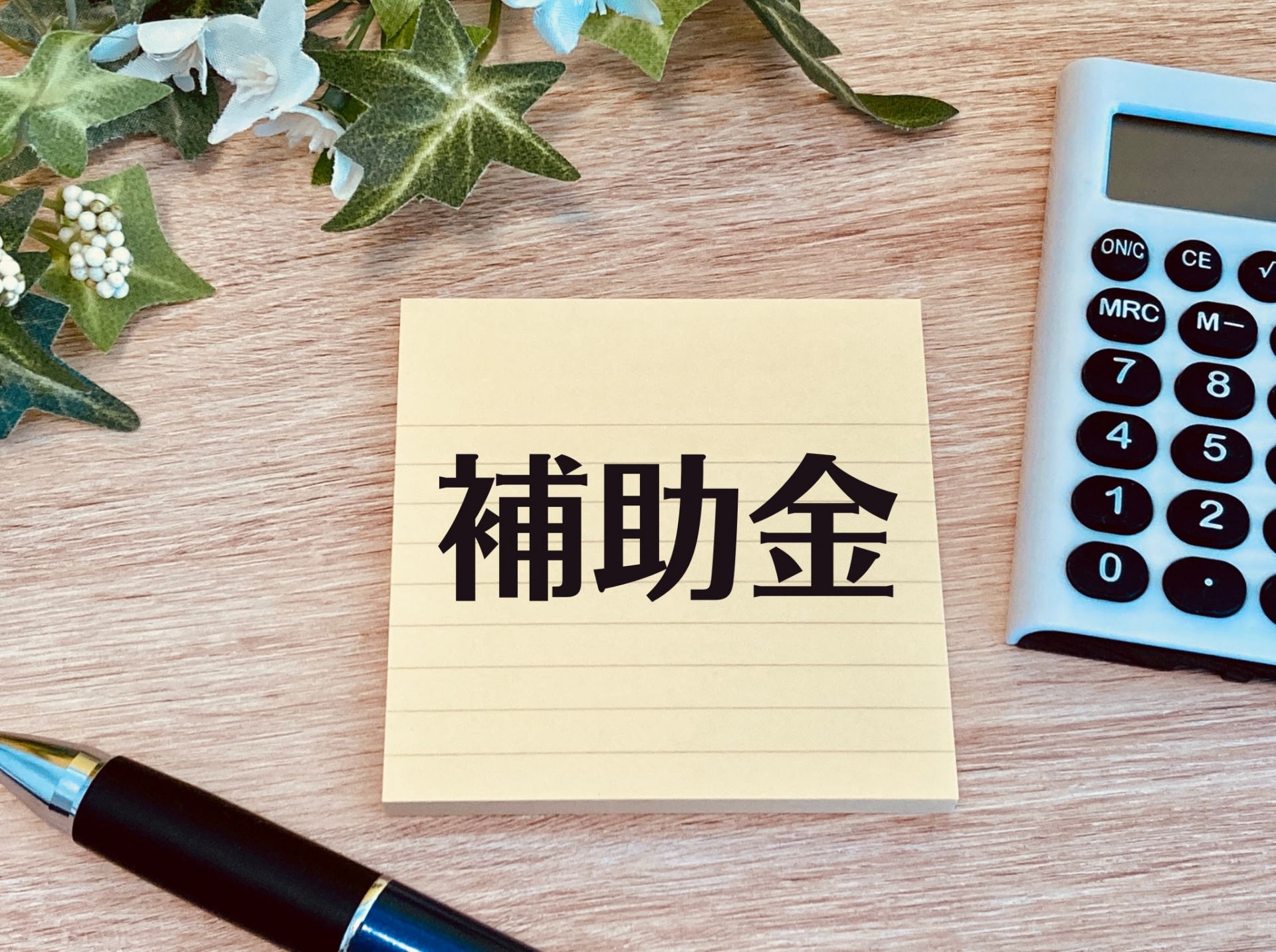
エイジフレンドリーは高年齢労働者の働きやすい職場づくりを目指す取り組みですが、それを後押しするのが「エイジフレンドリー補助金」です。
これは、中小企業事業者が高齢者の身体的特性に配慮した設備の導入や、健康維持・増進に向けた取り組みを行う際に、必要な費用の一部を国が補助する制度です。特に、身体機能の低下を補う機器の設置や、運動指導などのプログラム導入を通じて、高齢者がより長く安全に働き続けられる環境づくりを後押しします。
エイジフレンドリー補助金のコースは?

厚生労働省が実施するエイジフレンドリー補助金には、複数のコースが用意されており、目的や内容に応じて必要な支援を受けられる仕組みです。
以下では、代表的な4つのコースを紹介します。
総合対策コース
総合対策コースは、高年齢労働者が安全に働ける職場づくりを総合的に支援するコースであり、専門家によるリスクアセスメントの実施と、その結果を踏まえた優先順位の高い労働災害防止対策(設備導入や工事など)に対する補助が受けられます。
補助率は4/5、上限額は100万円です。
職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)
職場環境改善コースは、特に熱中症対策に焦点を当て、高年齢労働者が暑熱環境下でも安全に働けるようにするための設備導入や環境整備に対して補助を受けられます。
補助率は1/2、上限額は100万円で、スポットクーラーや冷却服などの導入が対象となります。
転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース
高年齢労働者の転倒や腰痛リスクを軽減するため、理学療法士、健康運動指導士など専門家を招いて運動指導や身体機能チェックを実施する際の費用として補助が受けられます。
身体機能の評価から運動指導、身体機能の改善までサポートが受けられ、補助率は3/4、上限は100万円です。健康的な働き方の推進に効果的です。
コラボヘルスコース
コラボヘルスコースは、医療保険者と企業が連携して実施する労働者の健康保持・増進の取り組みに対し、経費の一部として補助が受け取れます。産業医や保健師などによる健康指導や、メンタルヘルス対策指導、禁煙支援などが対象で、補助率は3/4、上限30万円です。健康な経営やエイジフレンドリーな職場づくりを推進するために活用できます。
出典:厚生労働省「令和7年度エイジフレンドリー補助金」のご案内」
従業員の健康意識向上は当社にご相談ください

エイジフレンドリーは、年齢に関係なく誰もが安心して働ける職場環境を整える取り組みです。従業員の健康意識を高めることは、企業全体の生産性や定着率の向上にも直結します。
当社では、従業員の健康を支援するサービス「アカルイミライ」を提供しています。健康診断データをもとにAIでリスク予測をし、生活習慣の改善をサポートすることで、従業員の健康意識と生産性の向上を目指しています。従業員の健康管理に関心のある企業様は、ぜひお問い合わせください。