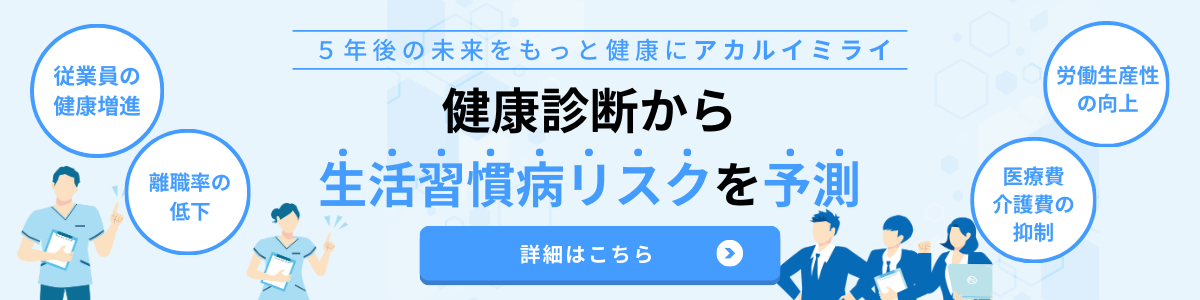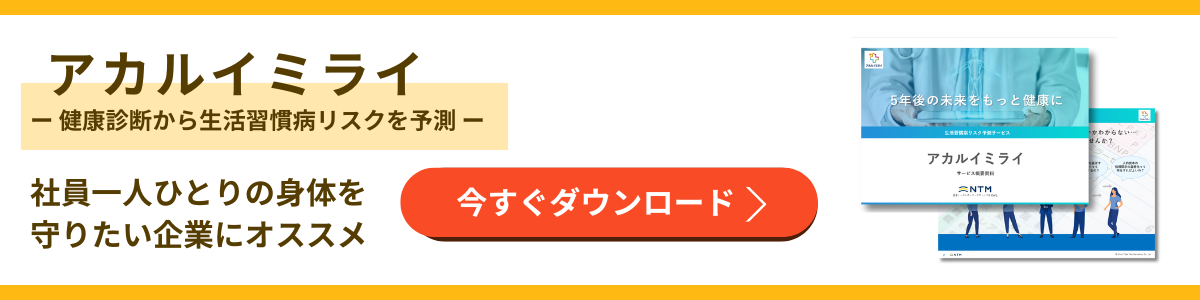健康経営とは?食事面からのアプローチや改善するメリットを紹介

少子高齢化が進行して働く人口が減少するなか、従業員の健康を確保することは企業が事業活動を継続させるために非常に重要な取り組みといえます。
そこで近年注目されている取り組みが「健康経営®」です。健康経営は、企業価値や業績の向上に寄与する取り組みと考えられています。なかでも「食事」は、健康的な体をつくるうえで欠かせない要素の1つです。
今回は、健康経営の概要や食事面での課題、取り組みのポイント、企業の取り組み例などについて解説します。食事を通して従業員の健康維持・増進を図りたい方は、参考にしてください。
目次
健康経営とは

健康経営とは、従業員の健康管理を経営的な視点で捉えて戦略的に投資することです。
企業が従業員の健康維持・増進に取り組むことにより、仕事への活力が高まり、パフォーマンスを最大限に発揮できるようになります。これにより、組織の活性化や生産性の向上につながると期待されます。
また、健康経営を通じて従業員の会社への貢献意欲やモチベーションといったエンゲージメントや企業イメージが高まることも期待できます。人材を経営に不可欠な資本と捉えて投資をすることは、企業価値の向上に結びつき、ステークホルダーからよい評価を得られるようになります。
出典:経済産業省「健康経営」
健康問題につながる食事の特徴

健康経営に取り組むうえで重視する要素の1つが「食事」です。心身の健康を維持するには、栄養バランスの取れた規則的な食生活が重要となります。
以下に当てはまる人は、健康問題を招きやすいと考えられます。
▼健康問題を招きやすい食事
- 栄養バランスが悪い
- 朝食を抜いている
- 食事の時間が不規則
- 野菜不足
- 塩分が多い
農林水産庁の調査によると、特に20〜39歳の若い世代は食生活に問題があることが分かっています。例えば、若い世代(20~39歳)では、「主食・主菜・副菜がそろった栄養バランスに配慮した食事を1日に2回以上ほぼ毎日取っている人は、28.3%にとどまります。また、朝食を取る頻度については、「週2〜3日食べる」と回答した人は9.7%、「ほとんど食べない」と回答した人が18.7%です。
最近では、コンビニエンスストアや宅配アプリなどでお弁当を手軽に購入できるようになりました。しかし、コンビニエンスストアのお弁当や外食の料理は、栄養バランスが偏りやすいため、食生活の乱れにつながってしまいます。
出典:農林水産省「食育に関する意識調査報告書」
健康経営で食事を改善するメリット

健康的な身体をつくるには、食事が基本となります。
ここでは、健康経営を通じて食事の改善をサポートするメリットを紹介します。
従業員のパフォーマンスが向上する
食事を改善すると、従業員のパフォーマンス向上が期待できます。栄養バランスの取れた食事を取ることで、体調不良の防止や集中力の向上につながると考えられます。
また、良好な食生活は、身体的な健康だけでなく精神面にもよい影響をもたらします。健康状態がよくなると活力が生まれ、仕事のモチベーションも高まると期待されます。このような好循環が生み出されることにより、生産性や業績の向上に結びつきます。
休職率や離職率が減る
食生活は、生活習慣病と深い関わりがあります。特に高血圧や糖尿病、肥満などは食生活との関連があるとされており、生命に関わる疾病につながるリスクもあります。
食事面からの健康支援に取り組むことで、従業員の健康状態が改善され、生活習慣病などの疾病予防につながります。結果として、休職率や離職率が減り、組織全体の生産性向上が期待されます。
出典:厚生労働省「栄養・食生活」
健康関連コストを削減できる
健康経営の一環として食事の改善に取り組むことで、従業員の健康問題によって生じる企業の健康関連コストの削減を図れます。
▼企業が負担する従業員の健康関連コスト
- 医療費
- 傷病手当金
- 労災給付金 など
また、病気や心身の不調によって業務の生産性が低下したり、欠勤・休職に至ったりした場合には、労働生産性の低下を招きコストの損失につながります。
企業の健康関連コストの中でも、健康問題による生産性の低下(=プレゼンティーズム)は大きな割合を占めるとされます。食事の改善を通じて従業員の健康を維持・向上させることは、労働生産性の損失を防ぐうえでも重要です。
出典:厚生労働省「産業保健の現状と課題に関する参考資料」
企業イメージの向上につながる
食事の改善支援は、企業のイメージ向上につながります。
近年、人材への投資を企業の価値創造の手段と捉える「人的資本経営」や、企業の「CSR(社会的責任)」が重要視されており、社会全体で健康経営への関心が高まっています。
積極的に健康経営に取り組む企業は、「従業員を大切にする企業」として求職者や投資家などから評価を得やすくなります。その結果、優秀な人材の確保や株価の上昇などにつながると期待されます。
健康経営に取り組むポイント
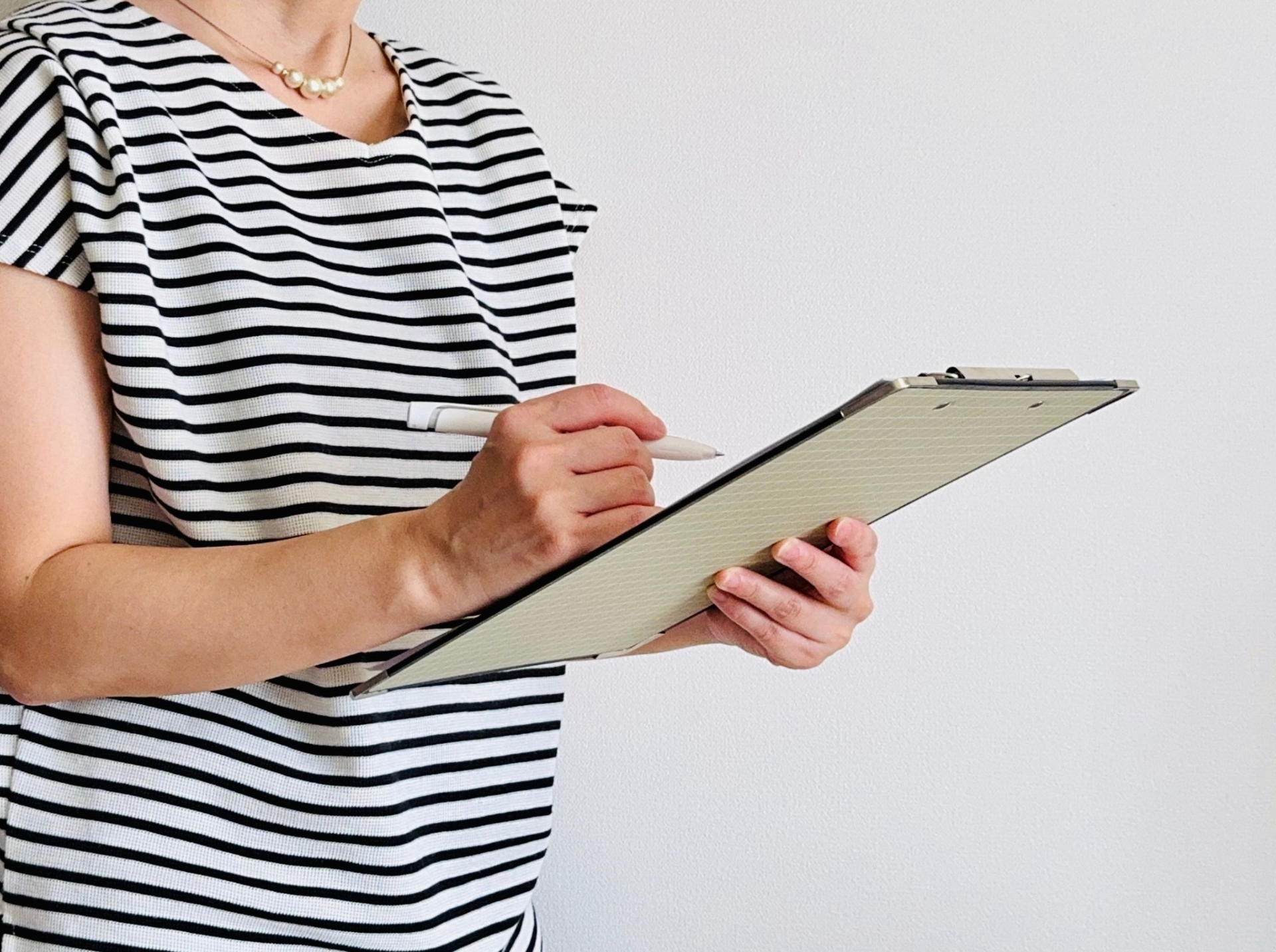
健康経営を推進するには、従業員の意識・行動を変容させて積極的な参加を促す必要があります。
ここからは、健康経営に取り組むポイントを解説します。
①意義や目的を明文化する
健康経営の意義や目的を明文化して社内外に発信することが重要です。
組織のトップが健康経営に対する方針を発信することで、社内全体や保険者などを巻き込んで健康課題に対する取り組みを促進できます。また、従業員の理解を得ることによって、社内全体で健康維持・増進に取り組む風土を醸成できます。
健康経営に取り組む社内の担当部署のほか、産業医、専門家、保険組合などと連携するチームを整備すると、健康経営の実効性を高められます。
②従業員の声を聞く
健康経営の施策を検討する際は、従業員の声を聞くことが重要です。
従業員が持つ課題やニーズを具体的に把握することで、健康維持・増進のために必要な支援や制度を導入できるようになります。
従業員との面談やアンケートを実施して、心身の健康や生活習慣、仕事のストレスなどに関する情報を収集することがポイントです。
③従業員への健康教育を実施する
従業員の行動変容を促すには、健康教育を実施して健康に対する意識やリテラシーの向上を図ることが不可欠です。
経営層が主体となって健康経営を推進しても、従業員が「自分にとって必要と思わない」「取り組み方が分からない」となると、生活習慣の改善は期待できません。
専門家による食育セミナーや栄養アドバイスなどを実施して、従業員に食事の大切さや健康づくりの正しい知識を伝えることが重要です。
最近では、AIやアプリを活用した健康管理にも注目が集まっています。例えば、食事が記録できるアプリを使えば、日々の食生活を手軽に可視化でき、継続的な健康改善に役立ちます。
④職場環境や風土を整える
健康経営を実現するには、心身ともに良好な状態で働ける職場環境や風土を整備することが欠かせません。
例えば、職場で体を動かしたり、休憩や気分転換をしたりする場所を設けることで、健康づくりに向けた日常的な行動を誘発できます。
また、社内コミュニケーションを活性化させるスペースの設置やイベントの開催は、風通しのよい組織風土をつくる取り組みといえます。仕事の不安や人間関係を原因とするメンタルヘルス不調の防止にもつながると期待されます。
特に日本人は同調傾向が強いため、「周りの人がやっているなら自分もやろう」と行動する人も少なくありません。社内全体で健康づくりに取り組む風土を醸成することで、健康に無関心な層も取り込むことが可能です。
⑤長期的に取り組む
健康経営の効果は、短期間で現れるものではありません。従業員の意識の変化や健康状態の改善などが目に見えるまでには時間がかかります。
着実に成果を出すためには、目標を設定して長期的な視点で継続して取り組むことがポイントです。定期的に施策の効果を分析してブラッシュアップしていくことで、投資効果に結びつくと期待できます。
食事を取り入れた健康経営の取り組み例

ここからは、食事にフォーカスした健康経営の取り組み例を紹介します。
食堂や社食の導入
栄養管理をサポートする方法として、食堂や社食の導入が挙げられます。
すでに食堂がある企業であれば、管理栄養士と連携して栄養バランスやエネルギー量に配慮した食事メニューを提供するとよいです。
また、低糖質で栄養バランスの取れたおかずプレートなど、管理栄養士監修の冷凍弁当を導入するのも有効です。宅配型や設置型を活用すれば、夜勤者や一人暮らしの従業員にも手軽に提供できます。
忙しい従業員が手軽に栄養のある食事を取れる環境を整えることで、健康経営の実行性をより高められます。
コンビニエンスストアのお弁当や外食で食生活が乱れがちな従業員の健康づくりをサポートすることが可能です。
食事に関するセミナーの開催
食事に関するセミナーを開催する方法です。セミナーを開催することで、健康的な食生活を送るための正しい知識や役立つ情報を提供できます。
また、管理栄養士や食生活アドバイザーに依頼して、従業員一人ひとりにアドバイスすることも有効です。手軽に栄養が取れる朝食メニューや、お酒が好きな人に向けた休肝日のメニューなどを紹介してくれるでしょう。
専門家によるセミナーやアドバイスを通じて従業員が食生活を見直すきっかけをつくることで、日常的な行動変容を促す効果が期待できます。
専門家への相談窓口の設置
従業員が専門家に相談できる窓口を設置することも、健康経営を推進する取り組みといえます。
食生活に関する習慣や悩みはそれぞれ異なります。画一的な食事指導ではなく、従業員一人ひとりの状況に合わせて専門的なアドバイスを受けられる環境を整備することで、食生活の改善を後押しできます。
例えば、管理栄養士や地域の保健センターの相談窓口が挙げられます。最近では、チャットツールを活用して専門家へ気軽に相談できる環境を整えている企業もあります。
食事による健康経営は当社にお任せください

心身の健康づくりには、食事をはじめとする生活習慣を整えることが欠かせません。健康経営を通じて生活習慣の改善につなげるには、従業員の健康状態やリスクに合わせたサポートが必要となります。
アカルイミライは、健康診断のデータに基づいたAIによる生活習慣病のリスク分析や、食事・運動などの日常生活のサポートを行えるサービスです。
一人ひとりの健康リスクを把握することにより、適切な保健指導が可能になり、従業員の行動改善を促せます。また、生活習慣の改善に役立つ情報をメールで送信することで、健康リテラシーと意識の向上が期待できます。
>>サービス詳細:未来の健康をAIが予想!アカルイミライ詳細はこちら
※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。