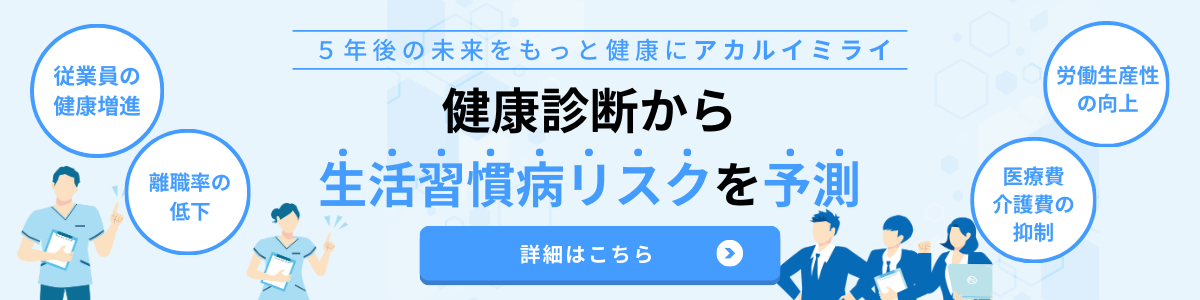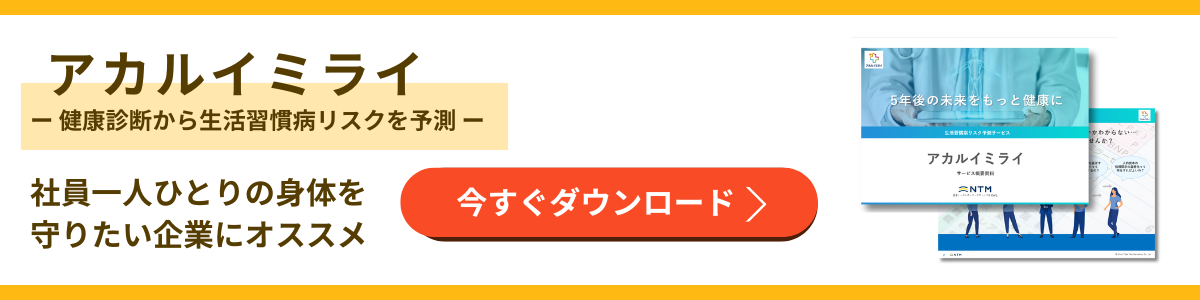アブセンティーズムとは?測定方法や企業の対策を紹介

近年、従業員の健康づくりを経営戦略として捉える考え方が注目されています。そこで重要なキーワードとされているのが「アブセンティーズム」です。
アブセンティーズムは、従業員の健康問題とパフォーマンスを紐づけて生産性を測る指標の1つです。今回は、アブセンティーズムの意味や測定方法、企業が取り組むべき対策について紹介します。
目次
- アブセンティーズムとは
- アブセンティーズムの原因
- プレゼンティーズムとの違い
- アブセンティーズムの測定方法
- ➀従業員へのアンケート調査を実施する
- ②欠勤や休職の日数を集計する
- ③休職の人数・日数を集計する
- アブセンティーズムが企業に与える影響
- 生産性が低下する
- コストが増加する
- 退職によって人材が流出する
- アブセンティーズムに対する企業の対策
- 健康経営を促進する
- ワークライフバランスを向上させる
- 従業員のメンタルヘルスを整える
- 従業員のセルフケアを推進する
- アブセンティーズムを改善する取り組み例
- 健康リテラシーを向上させるセミナーの開催
- 健康診断やストレスチェック後のフォロー
- 健康経営の推進は当社にお任せください。
アブセンティーズムとは

アブセンティーズムとは、心身の不調を理由に欠勤または休職することを指します。
健康問題に起因するパフォーマンスの損失を示す指標として、WHO(世界保健機関)によって提唱されました。
健康問題によって就業が困難になるアブセンティーズムは、企業の生産性低下や医療関連の費用負担の増加を招く要因の1つとなり、組織に大きな影響をもたらします。
出典:経済産業省「健康経営オフィスレポート」
アブセンティーズムの原因
アブセンティーズムに陥る原因は、精神的不調と身体的不調の大きく2つが考えられます。
▼精神的不調と身体的不調の例
| 精神的不調 | 身体的不調 |
|---|---|
| ・睡眠や休養の不足 ・メンタルストレス ・うつ病 など |
・頭痛 ・腰痛 ・肩こり ・アレルギー ・感染症 など |
女性特有の月経や月経前症候群(PMS)もアブセンティーズムの原因となり得ます。
精神的または身体的な不調が生じる要因には、仕事による過重な業務負担や生活習慣の乱れが関連しているケースもあり、企業には対策が求められます。
プレゼンティーズムとの違い
健康問題によるパフォーマンスの損失を表す指標には、アブセンティーズムのほかに「プレゼンティーズム」があります。
プレゼンティーズムとは、会社に出勤しているものの、体調不良やメンタル不調などが原因となって業務効率が下がっている状態です。たとえば、以下のような状態を指します。
▼プレゼンティーズムの例
・集中力が低下して作業スピードが遅くなる
・不注意による作業ミスが増える など
アブセンティーズムは欠勤や休職の記録から気づきやすい一方、プレゼンティーズムは勤怠に現れないため外部から見えにくく、放置されがちです。
アブセンティーズムの測定方法

アブセンティーズムは、主に3つの方法で測定できます。
経済産業省の「企業の『健康経営』ガイドブック」において推奨される測定方法は、以下のとおりです。
➀従業員へのアンケート調査を実施する
従業員へのアンケート調査を実施して、「病気や体調不良を理由に仕事を何日休みましたか?」といった質問に回答してもらう方法です。
従業員の欠勤や早退の記録は勤怠管理のデータから確認できますが、従業員から伝えられる理由が正しいとは限りません。
アンケート調査によって健康問題を原因とした欠勤や早退、有給休暇の取得状況を把握することで、自己申告に基づいた正確なアブセンティーズムを把握できます。
ただし、アンケートの回収率が低い場合は、アブセンティーズムの測定値に関する信頼性が低下する可能性があるため、ほかの測定方法を組み合わせることが必要です。
出典:経済産業省「企業の「健康経営」ガイドブック」
②欠勤や休職の日数を集計する
勤怠管理のデータから欠勤や休職の日数を集計する方法です。
有給休暇取得後の欠勤・休職は、疾病が主な理由となることが多いと考えられています。そのため、『企業の「健康経営」ガイドブック』では、アブセンティーズムを測定する代替指標として用いることが推奨されています。
ただし、有給休暇の取得理由を正確に把握している企業は多くありません。休暇中に発生した病気による取得日数も含まれないため、実際のアブセンティーズムよりも過小評価される可能性があります。
出典:経済産業省「企業の「健康経営」ガイドブック」
③休職の人数・日数を集計する
企業が保有する人事労務データを基に、休職した従業員の人数と休職期間の日数を集計する方法があります。
▼集計する情報
- 有給休暇を除く、30日以上の疾病による休職者
- 休職者の疾病名・休職理由
- 休職者の休職期間(開始日・終了日)
有給休暇の取得有無にかかわらず、疾病による30日以上の休職者全員の情報を集めてアブセンティーズムを測定することにより、的確な健康管理と復職支援につなげられます。
出典:経済産業省「企業の「健康経営」ガイドブック」
アブセンティーズムが企業に与える影響

アブセンティーズムは、従業員が働いていない状態を指すため、労働生産性の低下やコストの損失などのマイナスな影響をもたらします。
生産性が低下する
病気や体調不良が原因で働けなくなることは、生産性の低下に直結します。労働生産性の損失額は、アブセンティーズムの測定結果を基に算出できます。
▼アブセンティーズムによる労働生産性損失額
労働生産性損失額(円)= アブセンティーズム(日数)× 賃金(円)
また、欠勤や早退によって働く従業員の数が減ると、ほかの従業員に業務のしわ寄せが生じて、プレゼンティーズムまたはアブセンティーズムが増える悪循環に陥りやすくなります。
生産性の低下によって業務の停滞や遅延が発生すると、顧客からの信用が失われてしまい、経営にも大きな影響を及ぼすリスクがあります。
コストが増加する
アブセンティーズムは、人材や医療関連に関するコストの増加にも影響を与えます。
欠勤や休職によって人手が足りなくなった場合には、ほかの従業員への残業代や新たに人材を採用・育成するコストが発生します。
また、病気によって通院・入院が必要になると、企業における医療費や傷病手当などの負担額も増える可能性があります。
退職によって人材が流出する
病気や心身の不調を抱える従業員は、退職してしまう可能性があります。
優秀な人材が流出すると、知識やノウハウが失われるほか、採用や育成に充てたコストを損失につながります。また、ほかの従業員に業務が集中して負担が増えることにより、さらなる欠勤者の増加や退職につながる可能性もあります。
アブセンティーズムに対する企業の対策

アブセンティーズムの改善を図るには、従業員の健康維持・増進に取り組むとともに、心身の負担を軽減する職場環境への見直しを図ることが重要です。
健康経営を促進する
健康経営®は、企業が従業員の健康を重要な経営資源と捉えて、戦略的に投資する取り組みです。
生活習慣病やメンタル不調の予防、健康意識の向上などに向けた取り組みを実施することで、アブセンティーズムを防止できます。また、心身の健康づくりは、従業員の活力向上や組織の活性化にもつながります。
▼健康経営の取り組み例
- 生活習慣病や睡眠に関するセミナーの開催
- 社内または提携のトレーニングジムの導入
- 産業医や専門医による定期的な健康相談の実施 など
出典:経済産業省「健康経営」
ワークライフバランスを向上させる
ワークライフバランスとは、仕事とプライベートの調和を確保することです。
従業員のワークライフバランスを向上させる施策によって、心身をリフレッシュして仕事のストレスを軽減したり、十分な休養時間を促したりできます。その結果、疲労による体調不良やメンタル不調を防ぎ、アブセンティーズムの減少につながります。
▼ワークライフバランスを向上させる取り組み例
- テレワークやフレックスタイム制度の導入
- 残業の削減
- 育児や介護に関する支援制度の拡大
- リフレッシュ休暇制度の導入 など
従業員のメンタルヘルスを整える
従業員のメンタル不調は、上司や同僚などの周りの人が気づきにくく、欠勤・休職になってから発覚することも少なくありません。アブセンティーズムを減らすには、従業員のきめ細かな観察とサポートが必要です。
▼メンタルヘルス対策の取り組み例
- 社内・社外の相談窓口の設置
- メンタルヘルスに関する勉強会の開催
- 従業員同士が交流できるイベントの開催
従業員のなかには「メンタル不調については職場の人に相談しにくい」と思う人もいるため、外部の施設や専門家を活用したアプローチを試みることが大切です。
従業員のセルフケアを推進する
アブセンティーズムを削減するには、日ごろから従業員自身がセルフケアに取り組むことが必要です。企業には、従業員の健康意識を高める啓発活動をはじめ、セルフケアをサポートする施策を取り入れることが求められます。
▼セルフケアを推進する取り組み例
- 心身の健康状態を測るセルフチェックの提供
- 正しいセルフケアの実践方法を伝える研修の実施
- 健康管理アプリの導入 など
従業員が健康に関する情報を気軽に入手・活用できるようにすると、自身の状態に合ったケアの実施を促進できます。
>>サービス資料:(無料)アカルイミライに関する資料はこちら
アブセンティーズムを改善する取り組み例

ここからは、アブセンティーズムを改善する具体的な取り組み例を紹介します。
健康リテラシーを向上させるセミナーの開催
さまざまな企業で、健康リテラシーを向上させるためのセミナーが開催されています。
生活習慣病やメンタル不調などに関する正しい知識と対策などを伝えることにより、従業員の健康意識が高まります。従業員の健康意識が高まると、一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組めるようになる効果も期待できます。
健康診断やストレスチェック後のフォロー
健康診断やストレスチェックを実施して終わりではなく、結果に応じて適切なフォローを実施することが欠かせません。
産業医や専門家と協力して、心身の健康に問題がある従業員の健康管理を支援することにより、早期の治療につなげられます。
また、健康問題の原因を把握することにより、仕事量や働き方の見直しなどを調整できるようになり、アブセンティーズムの防止につながります。
健康経営の推進は当社にお任せください。

企業には、従業員の心身の健康を維持・増進するための取り組みが求められます。
当社では、従業員の健康管理をサポートするサービス『アカルイミライ』を提供しています。
健康診断の結果に基づいたAIによる生活習慣病リスクの予測診断や、最適な食事・運動のアドバイスを通じて、行動改善を支援します。
従業員の「生活習慣を改善させたい」、「健康診断をより効果的に活用したい」とお悩みの企業や自治体のご担当者さまはぜひこちらよりお問い合わせください。
※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。