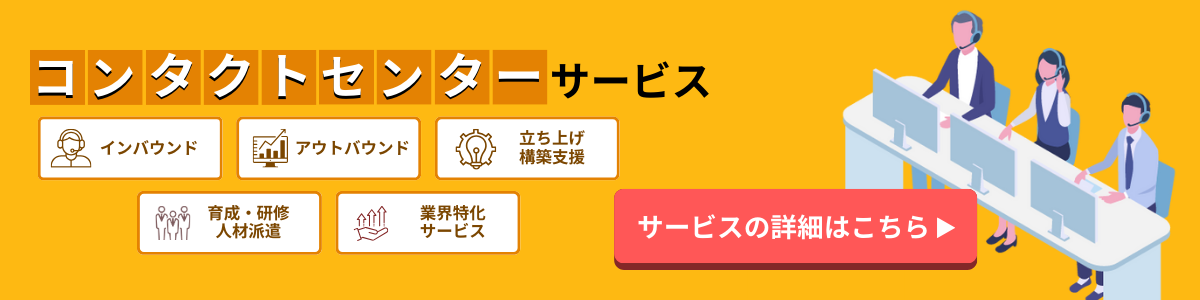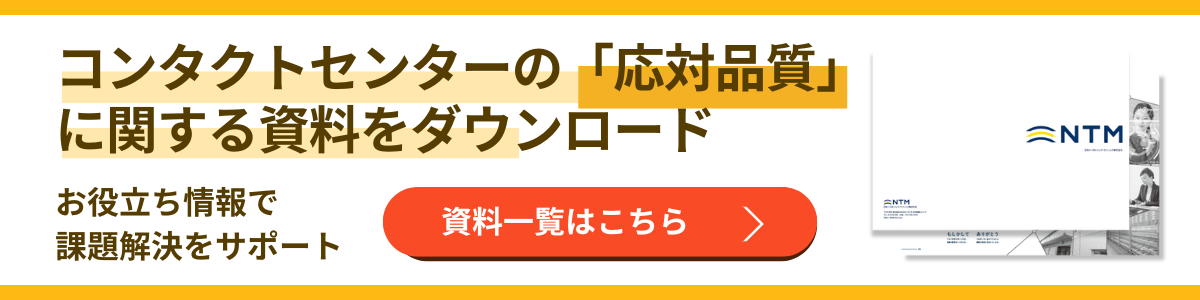コールセンターの評価指標や評価方法を一覧で解説!

企業と顧客をつなぐ窓口となるコールセンター(コンタクトセンター)では、オペレーターの応対品質によって企業全体のイメージが左右されます。
「品質を向上させたいけど、何から改善すればよいか分からない…」「評価制度を導入したけれど、なかなか定着しない」などとお悩みではありませんか?企業の顔となるコールセンターの品質を高めるには、適切な方法・指標を用いた評価が不可欠です。
この記事では、コールセンターで用いられる評価方法や主な指標などを網羅的に解説して、貴社の課題を解決するヒントをご紹介します。
目次
コールセンターを評価する目的

コールセンターは、企業の顔として顧客との重要な接点を担っています。オペレーターの応対品質を評価することには、主に3つの目的があります。
➀顧客満足度を向上させるため
1つ目の目的は、顧客満足度の向上を図ることです。
一定の評価基準を設けてオペレーターによる対応の均一化を目指すことで、社内における応対品質のばらつきを防いで安定した顧客体験を提供できます。
顧客の課題や問い合わせに対して的確かつ迅速に対応できるようになると、企業に対する印象アップにつながり、顧客満足度の向上に直結すると考えられます。
>>関連記事:コールセンター活用によるLTV最大化戦略~問い合わせ対応を価値創出に変える方法
②競争力を高めるため
2つ目の目的は、自社の競争力を高めることです。
コールセンターにおいて一人ひとりの回答内容や言葉づかいなどを可視化することで、評価結果に基づく継続的な改善活動を行えるようになり、応対品質の向上につなげられます。
オペレーターの対応を通じて顧客満足度が高まると、自社への信頼が深まり長期的な関係性を築くことが可能です。リピーターやファンの増加につながったり、良い評判が広まり新規顧客を獲得できたりする好循環を生み出すことで、市場における優位性を確立して競合他社との差別化を図れます。
③オペレーターを育成するため
3つ目の目的は、オペレーターを育成することです。
評価制度は、オペレーターの成長を促すための重要なツールになります。一人ひとりに対して評価結果のフィードバックを行うことで、パフォーマンスを客観的に把握でき、良い点をさらに伸ばしたり、課題を修正したりしてスキルアップを図れます。
成果や能力に対して公正な評価が受けられる環境を整えることは、従業員にとって働くモチベーションにつながり、人材の定着化やエンゲージメント向上にも結びつきます。
>>関連記事:コールセンターの研修とは? オペレーターのレベルに合わせた研修内容のご紹介
コールセンターの評価方法

コールセンターで行われる評価にはさまざまな方法があります。複数の方法を組み合わせることにより、多角的な視点からパフォーマンスを適正に評価できます。
| 評価方法 | 内容 |
|---|---|
| 上司による評価 | 上司がチェックシートなどを用いて総合的に評価 |
| モニタリングスコア | 言葉づかいや声の大きさなどを数値化して客観的に評価 |
| ミステリーコール | 担当者がお客様を装って電話し、実際の応対を確認 |
| 顧客へのアンケート | 顧客にアンケートを実施し、その結果により満足度を評価 |
NTMのコンタクトセンターサービスでは、音声およびテキストの応対品質を体系的に評価しており、オペレーターのスキルの標準化・向上に努めています。
通話品質評価システムの『AmiVoice』を使用して通話内容を一定基準で評価するとともに、声のトーンやイントネーションなどは人によって評価するハイブリッド方式を採用しています。
また、テキストについてはメール・チャットなどの文面を一定の基準に基づき数値化して、定量的な評価を行うことで品質の均一化を図っています。
コールセンターの評価項目

コールセンターの評価項目は、大きく分けてパフォーマンス・クオリティ・プロフィットの3つに分類されます。
➀パフォーマンス(効率)
パフォーマンスは、コールセンターの業務効率や生産性を測る評価項目です。オペレーターの業務処理能力やシステムの操作性などを評価するために設定します。
パフォーマンスを可視化することで、非効率な業務プロセスを見直したり、待ち時間が長い場合にオペレーター数を増やしたりする対策を講じられます。
②クオリティ(品質)
クオリティ(品質)は、オペレーターの応対品質や顧客満足度などを測る評価項目です。一人ひとりのスキルレベルを把握して課題を分析したり、教育による効果を測定したりする際に用いられます。
NTMのコンタクトセンターでは、オペレーター向けの研修カリキュラムを基礎編・応用編の2つから構成しており、応対品質の向上に取り組んでいます。
基礎編では、業務に必要な基本スキルを網羅的に学習して、NTM独自の高品質な応対の基盤を固めます。さらに応用編では、顧客の課題や状況を引き出すための研修や、コンサルティング力を強化する研修、必要に応じて美容・医療系に特化した専門研修も実施して、業種・業務内容に応じた満足度の高い対応を目指します。
③プロフィット(収益性)
プロフィットは、直接的・間接的な売上から収益性を見る評価項目です。
コールセンターにおいては、新規の契約やアップセル・クロスセルなどによる売上を直接的な収益として評価します。間接的な収益には、顧客ロイヤルティの向上によるLTV(顧客生涯価値)の向上や、顧客体験の向上による企業のイメージアップなどが挙げられます。
コールセンターを単なるコストセンターではなく、売上創出に貢献するプロフィットセンターとしての役割を果たすことで、企業全体の持続的な成長につながります。
>>サービス資料:(無料)コンタクトセンターサービスに関する資料はこちら
コールセンターの評価指標一覧

コールセンターの評価項目を測定する具体的な指標を一覧でご紹介します。
パフォーマンスの評価指標
パフォーマンスの評価指標には、以下が挙げられます。
| 評価指標 | 概要 |
|---|---|
| 応答率 | 機会損失と顧客離れを防ぐための重要指標 |
| 放棄呼率 | お客様が電話を切ってしまう割合 |
| 稼働率 | オペレーターが実際に稼働している時間の割合 |
| 占有率 | 業務時間に占める通話・後処理時間の割合 |
| CPH(平均処理件数) | 1時間あたりの処理件数 |
| ASA(平均応答速度) | 電話がつながるまでの平均時間 |
| SL(サービスレベル) | 設定時間内に応答できた件数の割合 |
| ATT(平均通話時間) | 1件あたりの平均通話時間 |
| AWT(平均保留時間) | 顧客を保留にする平均時間 |
| ACW(平均後処理時間) | 通話終了後の事務処理にかかる平均時間 |
| AHT(平均処理時間) | 通話から後処理完了までの平均時間 |
これらの指標を用いてパフォーマンスを評価することにより、「効率的に顧客対応ができているか」「顧客を待たせていないかなど」を把握して、運営体制の改善を図れます。
クオリティの評価指標
クオリティの評価指標には、以下が挙げられます。
| 評価指標 | 内容 |
|---|---|
| モニタリングスコア | 応対品質を数値化した総合評価 |
| 一次解決率 | 顧客の再問い合わせ防止、オペレーターの生産性向上に直結 |
| CS(顧客満足度) | 顧客アンケートによる満足度評価 |
| ミス発生率 | 業務処理におけるエラーの発生頻度 |
オペレーターの応対内容や顧客満足度などを評価することにより、一人ひとりの課題を把握して改善策を検討できます。よりよい顧客体験の提供や信頼関係の構築につなげるには、定期的にモニタリングを実施して継続的に改善活動に取り組むことが重要です。
プロフィットの評価指標
収益性を測定し、コールセンターの事業貢献度を評価する項目です。投資対効果の最大化を目指します。
| 評価指標 | 内容 |
|---|---|
| CPC(平均通話コスト) | 1件あたりの処理コスト |
| アップセル率・クロスセル率 | 追加商品・上位商品の販売成功率 |
| NPS(顧客推奨度) | 顧客がサービスを他者に推奨する度合い |
| 離職率 | 採用・教育コスト、顧客体験への影響を測定 |
| 売上・利益貢献 | コールセンター経由での売上・利益創出額 |
| CES(顧客努力指標) | 顧客が問題解決に要した労力の度合い |
これらの指標を基に収益性を測定することで、「どのような改善点があるか」「収益向上のために何が必要か」を導き出すことができます。
その他の評価指標
前述した3つの評価項目に加えて、オペレーターの定性的な部分も評価することが求められます。
▼定性的な評価指標
- ヒアリング力
- 会話での表現力
- 問題解決力
- 言葉づかい
- 勤務態度 など
定量的な評価指標だけでなく、オペレーターによる応対の姿勢やコミュニケーションでの伝え方なども含めた多角的な評価を行うことで、課題の把握や応対品質向上のためのヒントを発見しやすくなります。
コールセンターの評価制度を構築するうえで大切なこと

コールセンターの評価制度を構築する際は、単なる“可視化”で終わることなく組織全体の成長につなげることが重要となります。
ここからは、評価制度を構築する際に押さえておきたいポイントを解説します。
評価の目的を明確にする
コールセンターで評価制度を導入する目的を明確にします。
顧客満足度の向上やオペレーターの育成、生産性の向上など、評価の目的を明確にすることで適切な評価項目・指標を設定できるようになります。
また、オペレーターに対して「何のために評価するのか」を説明することにより、フィードバックを通じた自発的なスキルアップを促すことが期待できます。
データ分析とフィードバックを実施する
評価指標を用いて測定した定量的なデータを分析してフィードバックに活かすことが重要です。
評価結果を分析する際は、部門別・オペレーター別・問い合わせ内容別などのドリルダウン形式(※)で現状課題を深く掘り下げることがポイントです。これにより漠然としたフィードバックではなく、具体的なデータに基づいた改善策を提示することが可能になります。
※ドリルダウンとは、データを階層別に分類して詳細なレベルに分析していく手法
客観的かつ具体的な評価基準を設定する
コールセンターの評価制度では、客観的かつ具体的な評価基準を設定する必要があります。
設定した各指標に対して評価基準が抽象的な場合には、担当者の主観によって評価結果にばらつきが生じてしまいます。段階的な評価レベルとそれを客観的に判断する基準を定めることにより、評価の公平性を保つことができます。
例えば、ヒアリング力のような定性的な評価項目では、「積極的に顧客の声に耳を傾ける」ではなく、「顧客の課題を2つ以上引き出す質問をする」のような項目に設定すると、目標や評価を明確にすることが可能です。
オペレーターによる自発的な行動改善を後押しする
コールセンターの評価制度は、単にオペレーターの良い点を評価したり、悪い点を注意したりするだけでなく、責任感の醸成や自発的な行動改善を後押しする役割があります。
ネガティブなフィードバックでは、一方的に解決策を指示するのではなく「どうすればよりよい対応ができるか」を一緒に考える姿勢が大切です。ポジティブなフィードバックでは、良い点を具体的に伝えて、オペレーターの自信とモチベーションを高めることがポイントといえます。
また、評価結果を伝える際に次の目標や行動計画を立てたり、表彰制度や資格取得支援制度を導入したりすることにより、自発的な成長を促せます。
評価制度を定期的に見直す
構築した評価制度は、定期的に見直す必要があります。
評価制度を運用するなかで「対応業務の追加で新たな評価指標が必要になる」「評価基準が厳しすぎてオペレーターのモチベーションが低下する」などのギャップが発生することがあります。
評価者とオペレーターの双方からフィードバックを収集して、より現場に即した評価制度になるようにブラッシュアップしていくことが重要です。定期的な見直しにより、評価制度の形骸化を防いで精度を維持できます。
まとめ

コールセンターの評価制度は、オペレーターのパフォーマンスや応対品質を可視化して、現状課題に応じた改善策につなげるために重要な役割があります。
NTMのコンタクトセンターサービスでは、品質管理部を設置して一定基準以上の応対品質を維持できるように取り組んでいます。モニタリング・評価の実施とオペレーターの育成により、顧客満足度につながる高品質な対応を実現します。
電話以外のチャネルや幅広い業種業態にも対応しており、貴社の収益拡大や安定した顧客関係の維持をサポートいたします。詳しくはこちらをご確認ください。