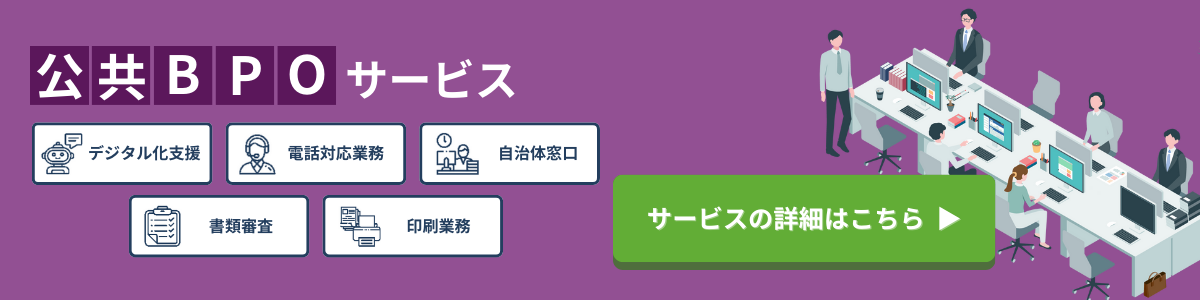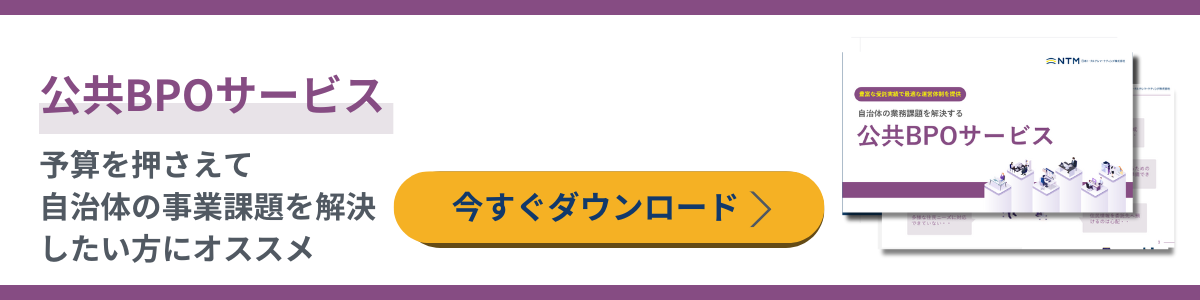行政のデジタル化の課題は?自治体DXの進め方やポイントを解説

行政のデジタル化は、自治体DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するための重要なプロセスの1つです。
窓口対応や紙媒体による行政手続きをデジタル化することで、業務の効率化や住民サービスの向上が期待できます。しかし、行政のデジタル化にはさまざまな課題があり、十分に推進できていない地方自治体も少なくありません。
今回は、自治体DXの第一歩となる行政のデジタル化に関する課題や進め方、推進するポイントについて解説します。
目次
行政のデジタル化における課題

DXを推進するうえで欠かせない行政のデジタル化ですが、地方自治体が有する人材や財源には限りがあり、積極的な取り組みが難しい場合があります。行政のデジタル化において地方自治体が抱える課題には、以下の6つが挙げられます。
デジタル人材の不足
行政のデジタル化を実施するデジタル人材がいない、または不足している課題があります。
行政のデジタル化を通じてDXを推進するには、ICTに関する知識・技術・ノウハウを持つ人材が不可欠です。しかし、地方自治体の職員のなかにデジタル人材がいるケースは少なく、外部人材の活用または育成が必要になります。
また、日本ではデジタル人材が不足しています。社会全体でデジタル人材の需要が高まるなか、地方自治体が採用活動を実施しても人材を確保できない可能性も考えられます。
既存業務の負荷
職員が対応する既存業務の負荷が大きく、デジタル化の推進に費やす時間と労力を確保できない可能性があります。
地方自治体では、多種多様な業務に限られた人員で対応しなければならないほか、地方公務員の定員削減や若手職員の離職率増加などによって、1人あたりの業務量が増えやすい傾向にあります。
デジタル化の推進は業務効率化を図るために有効な施策ですが、目の前の業務遂行にリソースを取られてしまい、後回しにされやすくなっています。
住民への周知不足
地方自治体がデジタル化に着手しても、住民への周知が不足すると効果を最大限に発揮できないおそれがあります。例えば、新たな制度や行政サービスを導入したにもかかわらず、住民の理解を得られずにデジタル化が形骸化してしまうケースが考えられます。
デジタル化を皮切りに地方自治体のDXを推進するには、住民への十分な説明と情報提供を実施して、理解を得ることが欠かせません。また、デジタル化の導入後は住民からの問い合わせ対応や高齢者へのサポートなども欠かさず取り組む必要があります。
財源の不足
行政のデジタル化には相応の資金が必要になります。導入するシステムの規模が大きければ大きいほど、開発費用も増大すると考えられます。
財源が限られている地方自治体では、デジタル化の予算を十分に確保しにくい面があります。また、「費用対効果が分からない」といった不安からDXへの積極的な投資が行われず、住民サービスの分野に予算を回している地方自治体も見られています。
アナログ文化の根強さ
アナログ文化が根強く残っていることも課題の1つです。地方自治体では、行政手続きや申請・承認のフローを紙ベースで運用しているところが多くあります。
慣れ親しんだアナログの方法からデジタルへの切り替えに対して、職員から抵抗感を持たれる可能性があります。業務の変革に対して組織内の抵抗が生じると、紙ベースの運用を廃止することが難しいため、長年にわたってアナログ文化が続いているケースがあります。
デジタル技術の年代格差
行政のデジタル化を進めるには、現場の職員がデジタル技術を活用する知識・スキルが必要になります。しかし、デジタル技術への理解や知識は世代によって格差があるため、ツールやシステムを使いこなせない職員が現れる可能性があります。
例えば、紙ベースの業務に慣れたベテラン職員と、デジタルネイティブにあたる若手職員の間では、デジタル技術への理解度に差が生じるでしょう。また、年代格差は住民の間でも生じます。特に高齢化が顕著な地方自治体では、デジタル化を定着させるハードルが高くなると考えられます。
行政のデジタル化を推進する取り組み
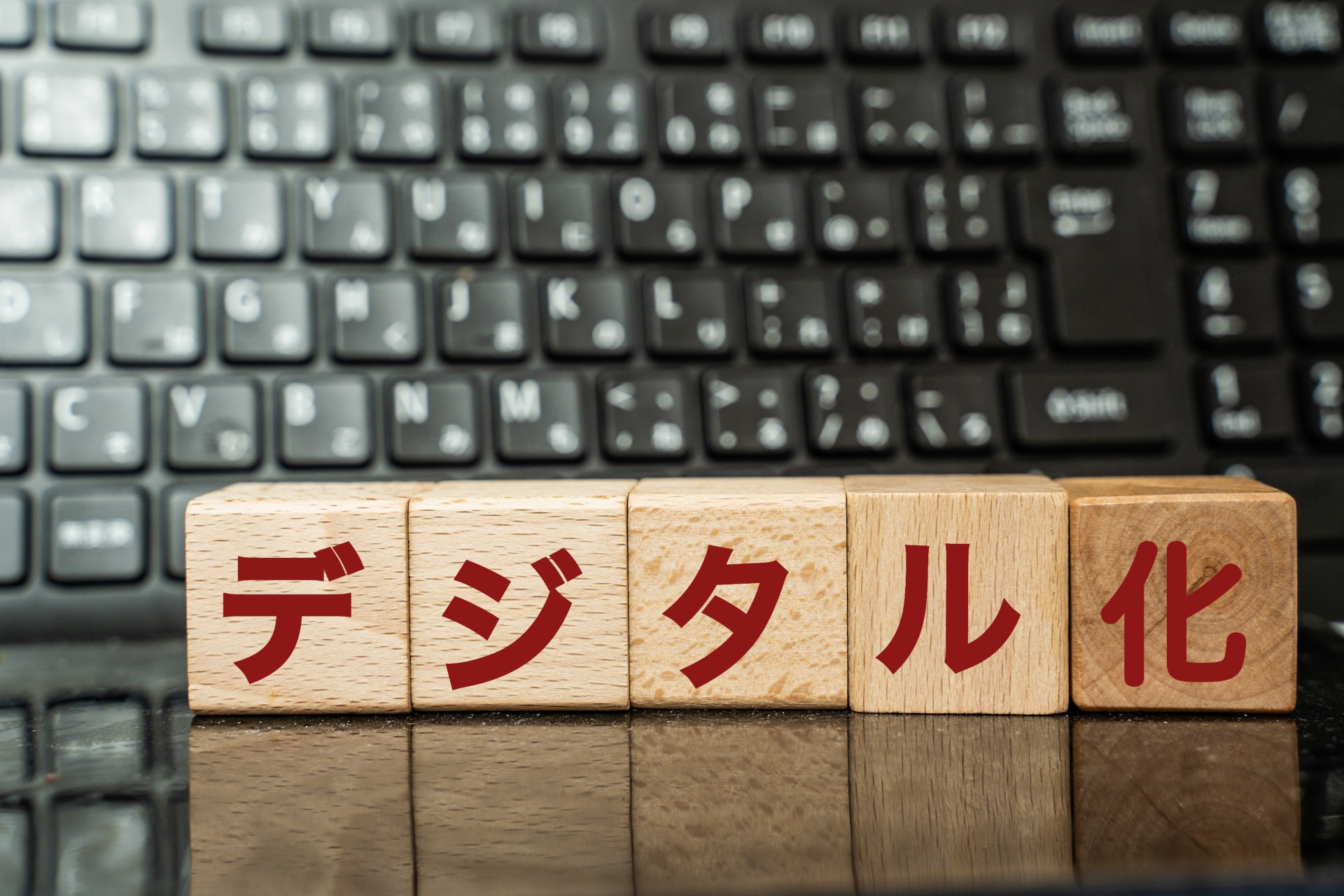
自治体DXを推進するには、行政のデジタル化がポイントとなります。紙媒体または対面によって運用していた行政サービスや業務をデジタル化することで、地方自治体の業務効率化と住民の利便性向上が期待できます。
ここでは、自治体DXに欠かせない行政のデジタル化を進める取り組みについて解説します。
➀「書かない窓口」の導入
「書かない窓口」とは、従来の紙を使ったアナログな申請手続きをデジタル化し、住民が申請書を手書きすることなく、よりスムーズに行政手続きを行える仕組みです。申請者は、スマホやタブレットを使って事前に必要な情報を入力し、窓口ではQRコードを提示することで、申請内容を迅速に処理できます。あとは署名するだけで、手続きが完了します。
この仕組みにより、窓口での対応時間が短縮されるほか、記入ミスや確認作業の負担も大幅に軽減されます。職員の業務負担が減ることで、より専門的な相談や対応に集中できるようになります。また、申請データはそのままバックヤード業務にも活用されるため、業務の集約化や効率化も進みます。
「書かない窓口」は、住民にとって利便性の高いサービスであると同時に、自治体にとっても業務効率の向上や資源の最適配分を実現する、自治体DXの中核を担う重要な取り組みです。
▼書かない窓口によるデジタル化の例
・窓口でタブレットを活用し、紙ではなくデータで手続き処理
・スマホアプリで事前に申請情報を入力し、QRコードを窓口端末で読み取り申請書を発行
・事前入力済みの申請書を印刷し、住民は署名するだけで完了 など
出典:総務省「自治体フロントヤード改革に関する個別取組事例集」
②オンライン申請の導入
オンライン申請は、対面での申請が必要だった行政手続きをオンラインで完結できるようにする仕組みです。マイナンバーカードの普及に伴い、住民がスマホやタブレットから手続きを行える基盤が整えられています。
国が運営する「マイナポータル」では、マイナンバーカードを用いてオンライン上で行政手続きができる機能が実装されています。地方自治体での行政手続きをオンライン化することで、「住民の利便性の向上」と「行政運営の簡素化・効率化」が期待できます。
なかでも処理件数が多く、オンライン化による効率化の効果が高いとされる手続きには、以下が挙げられます。
▼オンライン申請による効率化効果が期待される行政手続き
- 子育て関係・介護関係の手続き
- 罹災証明書の発行申請手続き
- 自動車保有関係手続き
- 転出届・転入予定市区町村への来庁予定の連絡 など
オンライン申請の導入には、マイナポータルの申請データを申請管理システムに取り込んで基幹システムと連携させるほか、LGWAN(※)端末からマイナポータル申請管理にアクセスして申請データを取得する方法などがあります。
※LGWAN:地方自治体間をつなぐ総合行政ネットワーク
出典:総務省「自治体の行政手続のオンライン化に係る手順書【第3.0版】」
③AI・RPAの活用
AI・RPAとは、業務の効率化を支援する技術で、RPAは決まった手順を自動で実行します。AIと組み合わせることで、問い合わせ対応や画像認識などに活用され、より柔軟な自動化が可能となります。地方自治体では、バックオフィス業務の効率化にAI・RPAの活用が有効です。手作業による定型業務やデータ集計、判断業務を自動化し、職員の負担を軽減できます。
▼AI・RPAの活用例
| デジタル技術 | 地方自治体の業務での活用例 |
|---|---|
| AI | ・チャットボットによる住民問い合わせ対応 ・画像・動画認識技術による道路管理に関するシステムの運用 ・AI-OCRによる申請書の読み取り |
| RPA | ・課税誤りに伴う課税異動業務のデータ化作業の自動化 ・転入者所得情報に関する連携業務の自動化 ・寄付⾦控除のシステム⼊⼒作業の自動化 など |
出典:総務省「自治体におけるAI・RPA活用促進」
④ガバメントクラウドの活用
ガバメントクラウドとは、「政府の情報システムについて、共通的な基盤・機能を提供する複数のクラウドサービス(IaaS、PaaS、SaaS)の利用環境であり、早期に整備し、運用を開始すること」です。
行政のデジタル化を通じて自治体DXを推進するには、基盤となる情報システムの標準化が必要となります。ガバメントクラウドを活用することで、例えば、各団体が個別にセキュリティー対策や運用監視を行う必要がなくなり、最新のセキュリティー対策の導入も可能となります。
また、地方自治体は、国が定めた標準に基づき、ベンダーが開発した「標準準拠システム」への移行をし、これによりシステム構築や管理の負担軽減が期待されます。
また、以下のようなメリットも期待されます。
▼ガバメントクラウドを活用するメリット
・サーバー、OS、アプリを共同で利用することで、コストの削減につながる
・新しいサービスを、より迅速に住民へ提供できるようになる
・住民が同じ情報を繰り返し入力する必要がない「ワンスオンリー」のサービスを提供しやすくなる
・個別の対応では難しい、最新のセキュリティー対策を導入できるようになる など
出典:総務省「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画 第3.0版」/内閣官房「地方自治体によるガバメントクラウドの活用について」
行政のデジタル化を推進するポイント

自治体DXの成功を目指すには、行政サービスのフロントだけでなくバックオフィスも含めてデジタル化による業務改革に取り組むことが重要です。行政のデジタル化をスムーズに進めるポイントには、以下が挙げられます。
組織全体での推進体制を構築する
地方自治体が行政のデジタル化に取り組むには、全庁的かつ横断的な推進体制の構築が必要です。行政のデジタル化においては、既存の業務フローが大きく変わることから、庁内でさまざまな意見の違いが生じる可能性があります。
効果的に推進するためには、デジタル化に対する意義や目的に関するメッセージを上位層から全職員に発信して、浸透させることが重要です。推進体制を立ち上げることで、ガバナンスのもと前向きな姿勢でデジタル化に取り組めるようになると考えられます。
▼デジタル化の推進体制を構築する際のポイント
- オンライン化の意義・目的・スケジュール・予算を首長に説明する
- ICTに知見がある職員と現場の業務に詳しい職員の協力体制を整備する
- 職位を問わずデジタル化に積極的な職員を取り入れる
なお、これらの対応は庁内のDX推進部門や情報政策部門などが主導となって進める必要があります。
デジタル人材を確保する
行政のデジタル化を推進するにあたっては、現場の実態に即して必要なデジタル技術を導入する際に、専門的な知見から判断・助言をするデジタル人材を確保する必要があります。
内部にデジタル人材がいない場合には、外部の事業者への委託や、新たにデジタル人材を任期付職員や特別職非常勤職員として任用する方法があります。
また、デジタル化による業務改革を実現するには、既存の職員に対してもデジタルリテラシーの向上を図ることが求められます。所属や職位に応じて、デジタル技術に関する知識・技能を習得させる体系的な育成制度を構築が重要です。
スモールスタートで取り組む
地方自治体の業務や行政サービスのすべてに対して、一度にデジタル化を進めることは難しいといえます。行政のデジタル化は、業務フローや住民サービスの利用方法を一変させるため、広範囲にわたる改革を進めると失敗のリスクが伴います。
着実に自治体DXを推進するには、優先度の高い業務から小規模な範囲でデジタル化に着手する「スモールスタート」での取り組みがポイントです。
デジタル化による業務改革や行政サービスのオンライン化などを通じて得られたノウハウを活かして試行錯誤しながら取り組むことにより、デジタル化の成果を得やすくなります。
>>サービス詳細:デジタルソリューションサービスの詳細はこちら
行政のデジタル化なら、当社にご相談ください

自治体DXを推進するにあたっては、行政サービスやアナログな業務のデジタル化に取り組むことが重要です。
行政のデジタル化は、業務の効率化や住民サービスの向上など、地方自治体に大きなメリットをもたらします。一方、デジタル化を推進させるうえで課題も存在します。デジタル人材の不足やアナログ文化の根強さに悩まされる地方自治体も多いことでしょう。
日本トータルテレマーケティングは、地方自治体向けにコールセンター運営やシステム構築業務、窓口業務、事務処理業務などをワンストップで提供しています。コールセンターAIチャットボットやマイナンバー・マイナポイントでのWeb予約システムの構築など幅広い分野で実績があり、多様なチャネルを通じた住民対応や業務委託支援を通じて、自治体における業務効率化の一助となります。