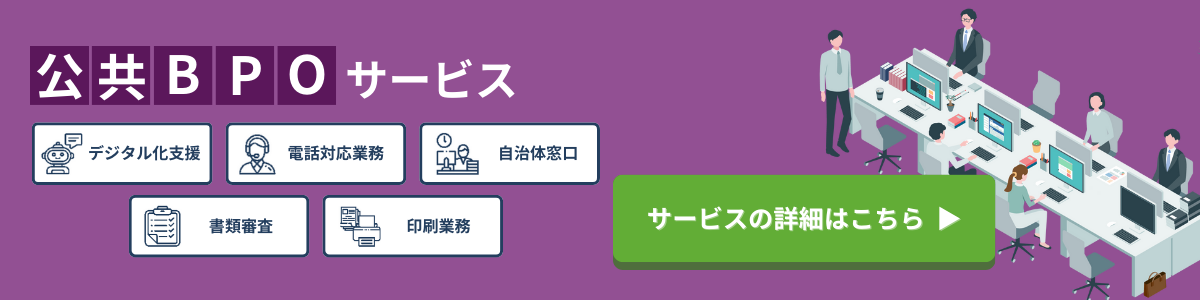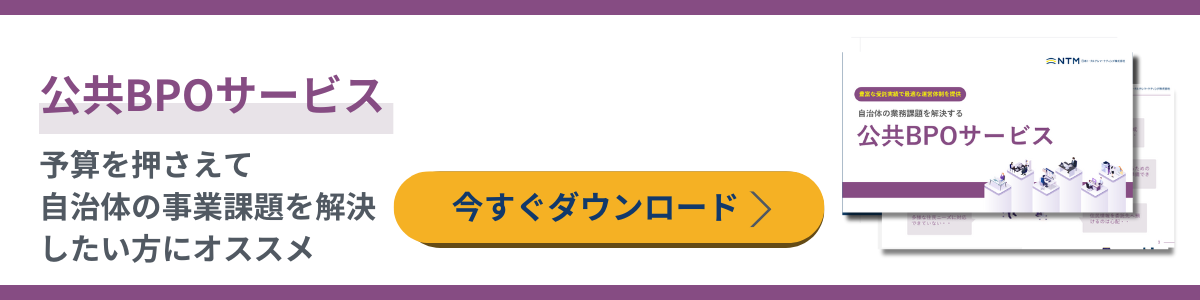指定管理者制度のメリットとデメリット|自治体・民間企業目線で解説

指定管理者制度とは、地方自治体が設置する公共施設の管理を民間事業者やNPO法人などに依頼する制度です。『地方自治法の一部を改正する法律』(平成15年法律第81号)により制度化されました。
指定管理者制度を活用すると、地方自治体と管理主体となる事業者の両者にメリットがあります。ただし、導入にあたってはデメリットについても理解しておく必要があります。
今回は、指定管理者制度の目的やメリット・デメリットについて紹介します。
出典:総務省「公の施設の指定管理者制度について」
目次
指定管理者制度の目的

指定管理者制度の目的には、おもに以下の3つが挙げられます。
▼指定管理者制度の目的
・民間事業者の活力を活用した住民サービスの向上
・施設管理における費用対効果の向上
・管理主体の選定手続きの透明化 など
民間事業者の知識やノウハウを活かすことで、住民ニーズに対応した質の高いサービス提供が可能になります。また、施設管理では、施設管理者に管理だけでなく効率的な運営を行わせることで、費用対効果の向上が期待されます。加えて、「指定の手続き」や「業務の範囲」などを条例で明文化することで、管理者選定の透明性を確保できます。
出典:総務省「公の施設の指定管理者制度について」「指定管理者制度について」
指定管理者制度の対象施設

指定管理者制度を導入できる対象は、地方自治体によって設置される公共施設のうち「住民の福祉を増進する目的で利用する施設」となります。例えば、以下の施設が挙げられます。
▼指定管理者制度の導入対象となる施設
- 体育施設(体育館・競技場・プール)
- 教育・文化施設(図書館・博物館)
- 社会福祉施設(特別養護老人ホーム・介護支援センター・福祉・保健センター)
- 大規模公園
- 公営住宅 など
市役所の庁舎をはじめとした行政事務を執行するための施設は、住民の福祉に関する利用が目的ではないため、指定管理者制度の対象施設には該当しません。国やほかの公共団体によって設置された施設も対象外です。
出典:総務省「指定管理者制度について」
【地方自治体側】指定管理者制度のメリット

2021年4月1日現在において、指定管理者制度が導入されている施設数は77,537施設あり、そのうち約4割の指定管理者が民間事業者となっています。ここからは、指定管理者制度を導入することで得られる主なメリットを解説します。
住民サービスの向上
1つ目は、住民サービスの向上です。
指定管理者制度を導入すると、民間事業者や非営利団体が持つノウハウを公共のサービスの企画・アイデアに活かすことが可能です。行政とは異なる視点から課題・ニーズを捉えられるため、より質の高い魅力的なサービスを提供できるようになります。
ニーズに合わせた多様なサービスを提供することで、住民の満足度・利便性の向上につながり、地域の魅力向上にも結びつくと考えられます。その結果、地域の活性化や観光産業の復興も期待できます。
経費の削減
2つ目は、経費の削減です。
公共施設の運営管理を民間事業者や非営利団体に依頼することで、効率的な運営が可能になります。地方自治体が対応していた施設管理業務を効率化・合理化できるため、運営経費の削減を図れます。
また、公募によって指定管理者を選定する仕組みによって、民間事業者間の競争が促されると考えられます。これにより、地方自治体が直営する場合と比べて、費用対効果が向上することが期待されます。
出典:総務省「指定管理者制度について」
【地方自治体側】指定管理者制度のデメリット

公共施設の所有者と運営管理を担う事業者が異なることにより、さまざまな問題が生じる可能性があります。地方自治体では、指定管理者制度のデメリットを理解したうえで、よりよい運営体制を構築することが求められます。
指定管理者の撤退リスク
1つ目は、指定管理者が撤退するリスクがあることです。
指定管理者制度では、3~5年の期間を定めて指定管理者を選定します。この指定期間が終了するタイミングで、指定管理者が撤退してしまう可能性があります。
指定管理者が撤退して新しい候補者が見つからない場合には、住民へ提供するサービスを継続できなくなるリスクがあります。また、民間事業者や非営利団体によって知識・ノウハウに差があるため、指定管理者が変わるとサービス品質の低下を招くことも考えられます。
出典:総務省「指定管理者制度について」
地域住民とのコミュニケーションの希薄化
2つ目は、地域住民とのコミュニケーションの希薄化です。
指定管理者制度を導入すると、地方自治体に代わって民間事業者や非営利団体が施設の運営を担うことになり、地方自治体の職員が地域住民と関わる接点が失われてしまいます。
これにより、施設保有者としての責任意識が低下したり、住民が抱える問題やニーズが地方自治体まで届きにくくなったりする可能性があります。
地方自治体では、指定管理者との密な対話のもとで、よりよい公共サービスの提供に向けて公民連携の体制を検討することが重要です。
【指定管理者側】指定管理者制度のメリット

指定管理者制度は、施設の運営管理を主体的に実施する指定管理者側にもさまざまなメリットがあります。
経営の安定化
1つ目は、経営の安定化です。
指定管理者として公共施設を運営すると、住民が支払った施設の利用料金を直接的な収益とすることが可能です。また、指定期間を5年とする施設が半数を超えており、なかには10年以上の施設も見られています。
地方自治体と長期的な協定を締結することで、一般的な業務委託と比べて安定した経営がしやすいといったメリットがあります。
出典:総務省「指定管理者制度について」
信頼性の向上
2つ目は、事業者としての信頼性の向上です。
指定管理者の選定は、議会の議決によって決定されます。事業計画書に加えて、住民平等利用の確保や差別的な扱いの禁止なども義務づけられています。
民間事業者や非営利団体が指定管理者として指定されることにより、社会的な信用を得やすくなり、地域住民やほかの民間企業からも信頼を得やすくなると期待されます。新たなビジネスチャンスを創出するうえでも有効な制度と考えられます。
【指定管理者側】指定管理者制度のデメリット

指定管理者のデメリットには、指定期間終了後に継続されず、蓄積したノウハウや経験が新たな民間企業に十分引き継がれない可能性があります。
また、指定管理者制度は効率化やコスト削減を目指していますが、その結果として、サービスの品質が低下するリスクもあります。
指定管理者制度を導入する流れ

地方自治体が指定管理者制度を導入する際、地方自治体は一定の手続きを踏む必要があります。ここでは、その導入の流れをわかりやすく解説します。
①条例の制定・改正
指定管理者制度を導入するには、地方自治体で条例を制定する必要があります。条例で定める事項には、おもに以下が挙げられます。
▼条例で定める事項
・指定管理者を選定するための「指定の手続」
・指定管理者に行わせる「業務の範囲」
・指定管理者の活動指針となる「管理の基準」
指定管理者として選定した民間事業者や非営利団体は、地方自治体が定めた条例に基づいて施設の運営管理を実施することになります。
出典:総務省「指定管理者制度について」
②公募による候補者の選定
指定管理者を選定する手続きは地方自治体によって異なりますが、公募を実施することが一般的です。Webなどからの公募要項の周知や説明会の開催により、指定管理者の候補者を集めます。そして、公募によって提出された事業計画書を基に指定管理者の候補を選定します。
③議会の議決・指定
公募で指定管理者の候補を選定したあと、地方自治体で議会の議決を実施します。対象施設や指定期間を定めて、指定管理者を決定します。
審査の基準は地方自治体によって異なりますが、事業計画書の内容や実効性などが確認されます。
④運営・管理
指定管理者が指定されると、協定を結び、公共施設の運営・管理が始まります。
指定管理者による運営に問題がある場合には、必要に応じて指定の取り消しや指示、業務停止命令が行われることもあります。
出典:総務省「指定管理者制度について」
指定管理者制度と他制度との違い
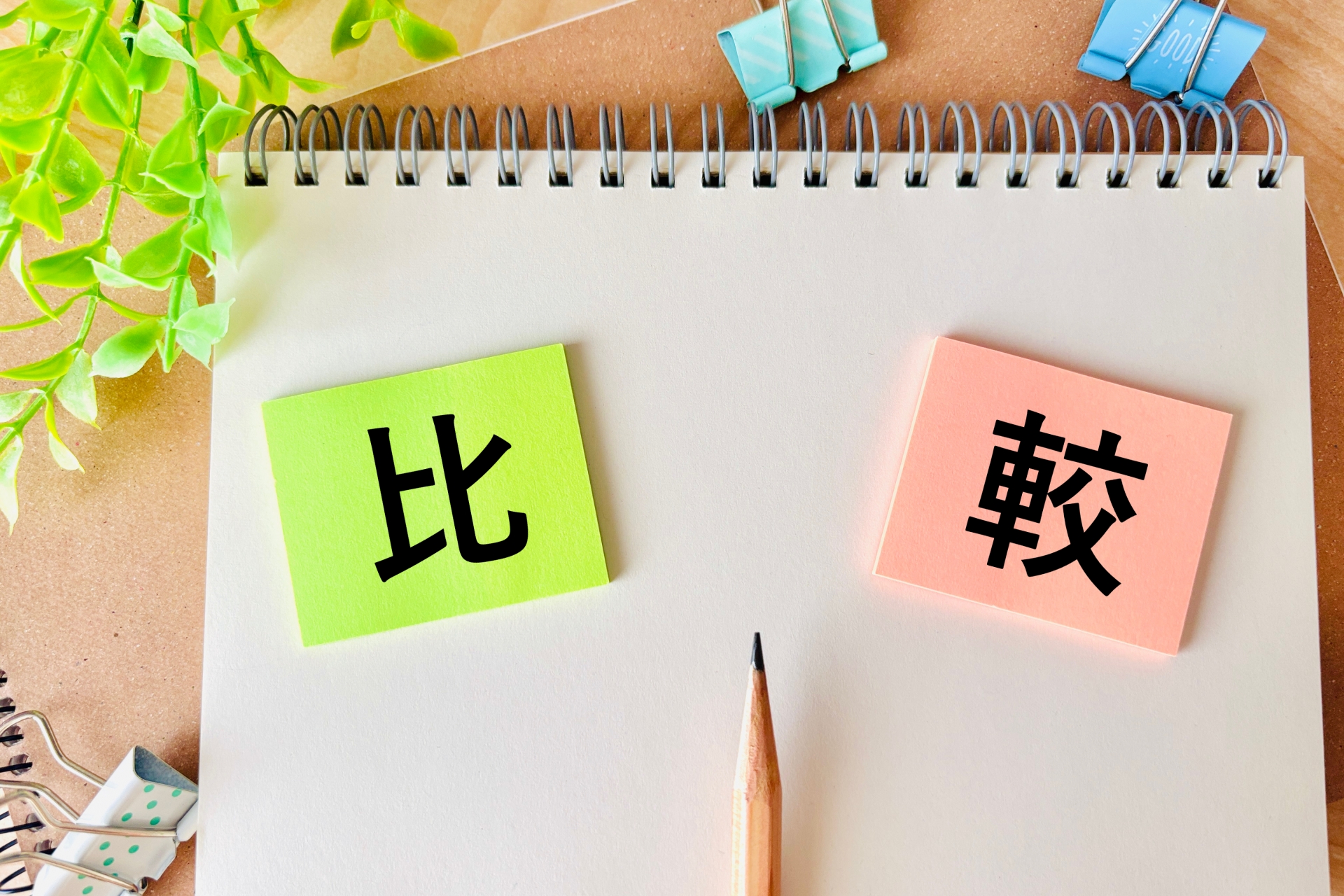
指定管理者制度のほかにも、公民連携によって公共施設を運営する手法があります。ここでは、指定管理者制度と混同されやすいほかの制度について紹介します。
PFIとの違い
PFI(Private Finance Initiative:プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)は、公共施設の設計・建築・維持管理・管理運営に民間事業者の資金・ノウハウを活用して、公共サービスを民間事業によって提供する制度です。
民間事業者が保有する経営上のノウハウ・技術を活用することで、質の高い公共サービスの提供や事業コストの削減、官民のパートナーシップの形成が期待されます。
指定管理者制度とPFIでは、法律や対象となる施設、委託する範囲などが異なります。
▼指定管理者制度とPFIの違い
| 指定管理者制度 | PFI | |
|---|---|---|
| 法律 | 地方自治法第244条の2 | PFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律) |
| 対象施設 | 地方自治法第244条の2で定められた「公の施設」 ┗住民福祉の増進に寄与する公共施設 |
指定管理制度の「公共施設」以外も対象 |
| 委託範囲 | 「公共施設」の運営管理のみ | 公共施設の設計、施工から運営にいたるまで |
対象施設や委託範囲は、指定管理者制度よりもPFIのほうが広くなっています。
出典:内閣府「PPP/PFIとは」「Q1 PFIとは」「用語集」
管理委託制度(従来制度)との違い
管理委託制度は、指定管理者制度が創設される法改正前にあった従来の制度です。
指定管理者制度と管理委託制度では、委託先の範囲、管理期間、施設の使用許可などに違いがあります。
▼指定管理者制度と管理委託制度の違い
| 指定管理者制度 | 管理委託制度 | |
|---|---|---|
| 委託先 | 法人その他の団体であれば、特段の制限なし | 公共団体・公共的団体・出資法人に限定 |
| 管理期間 | 期間を定めて指定する | 期間の定めなし |
| 使用許可 | 指定管理者ができる | 自治体だけが行える |
出典:総務省「指定管理者制度について」
公共BPOサービスは当社にご相談を

日本トータルテレマーケティングは、地方自治体向けにコールセンター運営やシステム構築業務、窓口業務、事務処理業務などをワンストップで提供しています。
コールセンターAIチャットボットやマイナンバー・マイナポイントでのWEB予約システムの構築など幅広い分野で実績があり、多様なチャネルを通じた住民対応や業務委託支援を通じて、自治体における業務効率化の一助となります。