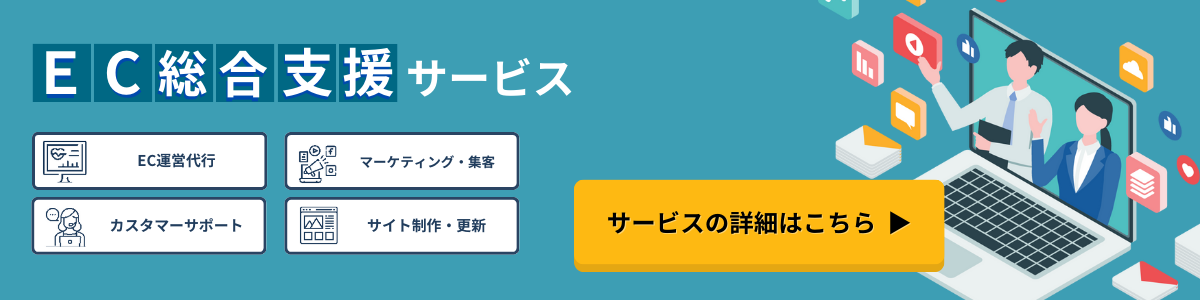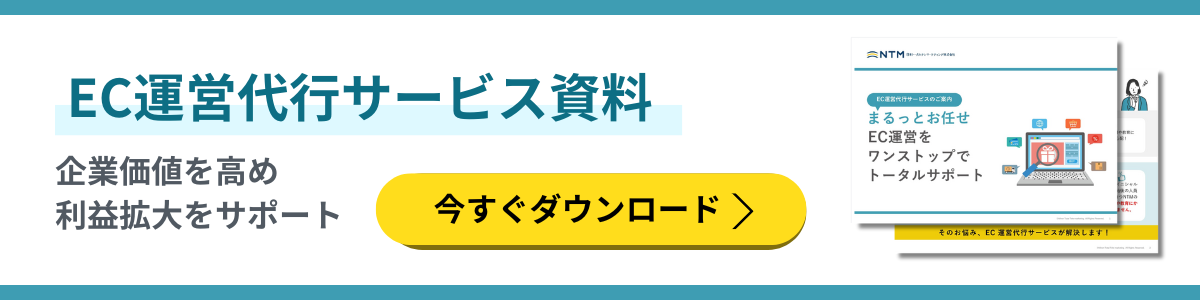LTVとは?EC事業で重視される指標であるLTVの意味と求め方、EC事業への活用方法を解説。

LTVとは、1人の顧客が同じサービスに対しどれほどの収益をもたらすかを表す指標です。ECサイトでは、LTVは事業の将来性や継続可能性を計る指標として活用されています。
LTVの意味や算出方法、EC事業への活用方法を解説します。
目次
-
LTVの意味と重要性
-
LTVはEC事業の指標として有効
-
EC業界におけるLTV
-
なぜEC業界で特にLTVが重視されるのか
-
LTVの計算方法
- 基本の式
- サブスクリプション型
- 長期契約型
- LTVと組み合わせて分析したい指標
-
ARPA・ARPU
-
チャーンレート
- CAC
- CRC
- ユニットエコノミクス
-
LTVを向上させるポイント
-
購入頻度を増やす
-
購入単価を大きくする
-
購入期間を長くする
- 収益率を高くする
-
顧客募集コスト・維持コストを下げる
- CPAで適切な広告費用を算出する
- 限界CPAの算出方法
-
CRMでLTVを向上させる
-
CRMとは
-
CRMとLTVの親和性
-
MAやチャットボットも有効
-
LTV向上のためのマーケティング施策
-
既存顧客の誘導
-
アップセルとクロスセル
-
休眠顧客復活の施策
-
EC運営代行会社の活用
- LTVでEC事業を発展させよう
LTVの意味と重要性

LTVは「Life Time Value」を略した言葉で、「顧客生涯価値」を意味します。具体的には、1人の顧客が生涯を通じて企業に投じる利益の総額を指します。
現在LTVの意義が重視されている背景には、新規顧客募集にかかるコストが既存顧客維持の5倍必要だという現状があります。企業同士が新規顧客の奪い合いをしても、費用対効果が悪く利益につながらないのです。
この状況を打破するため、既存顧客への働きかけを重視する観点からLTVが注目されています。
LTVはEC事業の指標として有効

EC事業は、近年大きく拡大している成長業種です。LTVが注目された理由の1つとして、EC事業においてもLTVが重要な指標となる点があげられます。
ここでは、EC事業とLTVの関係性について解説します。
EC業界におけるLTV
実店舗を持たないEC事業では、新規顧客の募集は既存顧客の維持よりはるかに難しくなります。ECサイトの利用が多くの人々にとって日常的行為になった結果、インターネット上に情報が氾濫し、既存の大手から新規に顧客を呼び寄せることが困難になったからです。
EC業界に限らず、広告自体がマスマーケティングからOnetoOneの傾向を強めている点も影響しています。
なぜEC業界で特にLTVが重視されるのか
EC業界でLTVが特に重視される理由は、EC事業を運営する際にLTVが新規顧客募集にかける予算の指標となるためです。
EC事業では、既存顧客のLTVに粗利率を乗じた数値を将来的に得られる利益とみなします。そして、その数値が新たな広告費の上限値となるのです。
EC事業では新規顧客募集のため広告費が必要ですが、過剰に広告費をかけて赤字となる事業も少なくありません。そのため、広告費の限界金額の基準が必要です。言い換えると、LTVが大きい事業は広告を打って顧客をより増やせる、つまり将来性が高いことを示しています。
LTVの計算方法
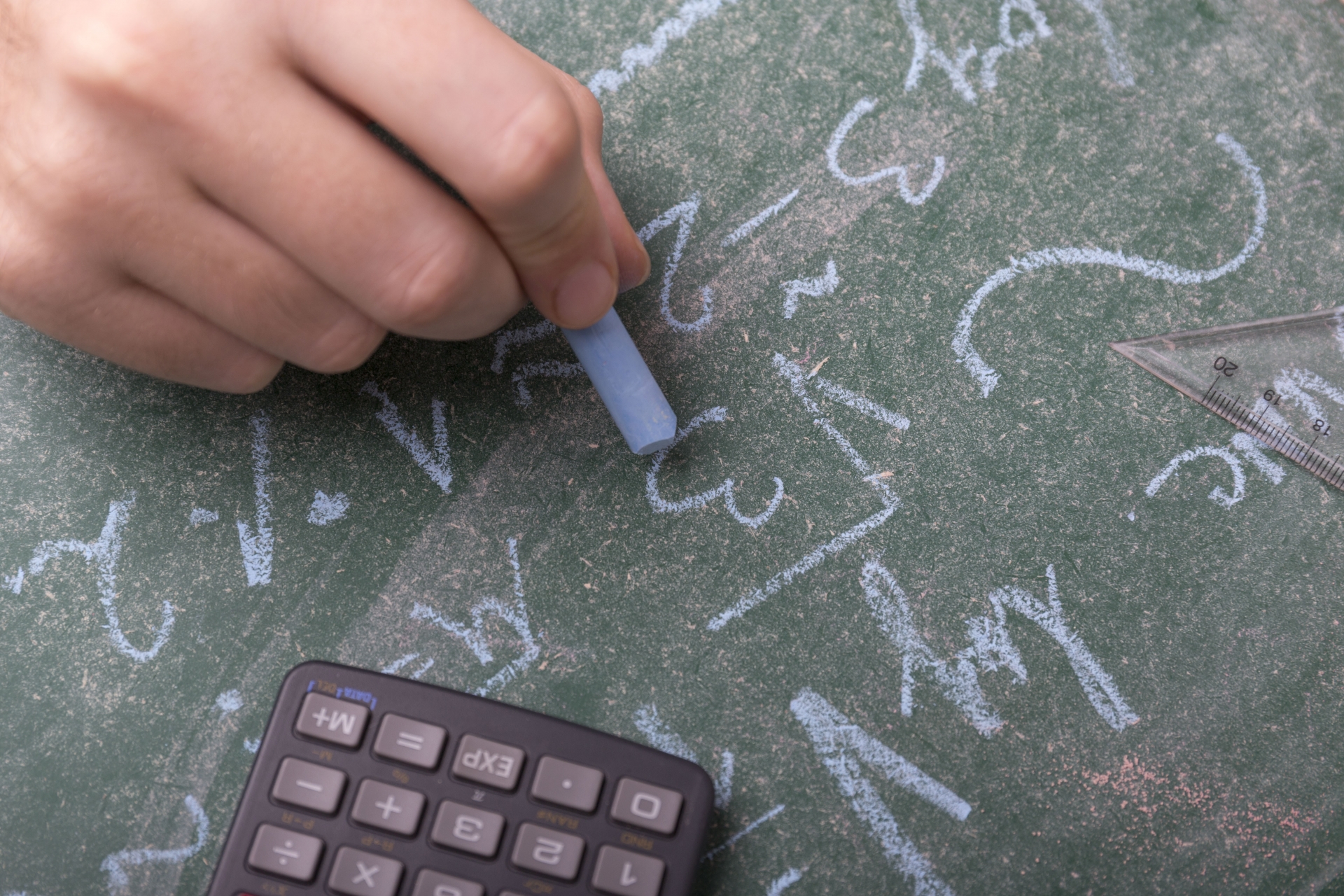
LTVの計算式には、いくつかの種類があります。
ここでは基本の式を紹介し、サブスクリプションサービスや長期契約型については別途説明します。
基本の式
LTV
=平均購買単価 × 購買頻度 × 継続期間 - (新規顧客募集コスト + 既存顧客維持コスト)
購買頻度、継続期間は顧客の平均値を用います。
既存顧客の維持コスト、新規顧客の募集コストを引いた値が純粋なLTVです。
アパレルブランドのECサイトで、平均購買単価12,000円、購買頻度1回/2か月、継続期間3年だとします。
新規顧客募集コストが28,000円/人、既存顧客維持コストが1,500円/人・月とすると、LTVの計算式は以下のようになり、LTVは134,000円です。
LTV
=12,000円×1回/2か月×36か月(3年)-(28,000円+1,500円/人・月×36か月)
=134,000円
サブスクリプション型
サブスクリプションサービスでは、LTVの計算式は次の形になります。
LTV=平均顧客単価 × 100 ÷ 解約率(%)
サブスクリプション型の販売モデルでは、解約率が大きな指標とされます。高い解約率の改善を目指す際には、LTVが指標として必要です。
平均顧客単価が15,000円で、解約率が12%である食品の定期購入サブスクリプションの場合を例に計算してみましょう。
サブスクリプションサービスでは、100%/解約率が平均継続期間として扱われます。解約率が20%のサービスでは、平均継続期間は5か月です。
LTV=15,000円/月×100/12%=125,000円
よってLTVは、125,000円となります。
長期契約型
長期契約のECサイトにおけるLTVは、1人の顧客の年間取引額をサイト利用継続年数の平均値に乗じて求めます。
LTV=年間取引額 × 粗利率 × 継続期間
ある企業がリモートの新人研修サービスを年2回、5年間利用したとします。
1回あたりの単価が50,000円、粗利が30%であるとすると計算式は以下のようになり、LTVは150,000円です。
LTV=50,000円×2回/年×0.3×5年=150,000円
LTVと組み合わせて分析したい指標
LTVの他に関連性の高い指標があります。
組み合わせて分析することで、LTVの最大化に寄与したり低下を予防したりと重要なデータの収集が可能です。
ここでは、組み合わせる指標の5つを紹介します。
ARPA・ARPU
ARPA(アーパ)は「Average Revenue per Account」の略称で、1アカウントあたりの平均売上額のことです。
ARPU(アープ)は「Average Revenue Per User」の略称で、1ユーザーあたりの平均売上額のことです。
2つの数値は、LTVの計算に必要な平均購入単価を指します
それぞれの計算式は次の通りです。
ARPA=売上額÷アカウント数
ARPU=売上額÷ユーザー数
ARPAは、サブスクリプション型や複数アカウントでの売上を知りたい場合の数値化に役立ちます。
ARPUは、ユーザーベースでの平均売上を知り、LTVの算出に使用可能です。
2つの数値の取り扱いは、サービスや商品の提供形態によって違います。
チャーンレート
チャーンレートとは、一定期間内にサービスや商品を利用しなくなった顧客の割合を表す指標で、「解約率」や「退会率」とも呼ばれます。
数ある指標のなかでも顧客満足度をダイレクトに示す指標とされており、定期購入や会員制のビジネスにおいては特に重視されることが多い指標です。
チャーンレートが低いと顧客の満足度が高く、解約率も低いと判断できます。
チャーンレートを下げることで継続利用率を上げ、既存顧客の維持やLTVの向上につながります。
特に、サブスクリプション型のLTV計算に必要な指標といえるでしょう。
チャーンレートには2種類あり、それぞれ計算式が違います。
| カスタマーチャーンレート | レベニューチャーンレート | |
|---|---|---|
| 内容 | 1か月の顧客を比較したの解約率 | 1か月の収益ベースでの解約率 |
| 計算式 | カスタマーチャーンレート(%)=1か月に解約した顧客数÷1か月前までの顧客数×100 | レベニューチャーンレート(%)=サービス単価×1か月に解約した顧客数÷1か月の総収益×100 |
CAC
CACとは「Customer Acquisition Cost」の略称で、新たな顧客を1人募集することにかかるコストを指す指標です。
この時のコストとは、営業活動に使われた人件費やイベント、広告などのマーケティング費など顧客募集にかかった費用は全てCACに含まれます。
商品やサービスの単価が高ければ高いほど、CACにかかる費用も高額になるのが一般的です。
ただし、CAC>LTVとなる場合は、顧客募集をすると損失が生まれるため要注意です。
CACは、以下の計算式から算出できます。
CAC=新規顧客募集にかかった全ての費用÷新規顧客数
CRC
CRCは「Customer Retention Costs」の略称で、既存顧客1人を維持することに必要なコストを指す指標です。
ここでのコストとは、メルマガや広告など既存顧客との関係維持に必要なマーケティング費や広告費、デジタルツールにかかる費用など、顧客維持のためにかかった全ての費用です。
既存顧客の維持は、顧客満足度に影響を与え、広告の効果を向上させることが期待できます。
ただし、CACとCRCが利益を圧迫する状況では、これらにかかる費用を下げる必要があります。
CACとCRCが低くなると、チャーンレートが高まる恐れがあるためバランスの見極めが重要です。
CRC算出に必要な計算式は、以下の通りです。
CRC=既存顧客維持にかかる全ての費用÷既存顧客数
ユニットエコノミクス
ユニットエコノミクスは顧客1人あたりの採算性のことです。
ユニットエコノミクスが適性である場合、「顧客募集のために費やすコスト」と「顧客募集後に得られる利益」とのバランスが取れており、事業として健全な状態であるといえます。
計算式は、以下の通りです。
ユニットエコノミクス=LTV÷CAC
LTVを向上させたり、CACの費用を抑えたりすると、ユニットエコノミクスは上がります。
一般的な基準の数値は3〜5、サブスクリプション型のサービスや製品では3以上といわれ、異なる基準を持つため、一定であればよいというものではありません。
顧客募集にかかったコストと、顧客から得られる利益のバランスを計る指標ともいえるでしょう。
ユニットエコノミクスは、期間や金額別に確認できるため、継続利用を見込んだ顧客がどのタイミングで採算性が高まるかを判断できます。
LTVを向上させるポイント

LTVは主に、購入頻度、購入単価、購入期間という3つの要素が影響しています。
加えて、商品・サービスの収益率、既存顧客の維持や新規顧客の募集にかかるコストの影響も大きいでしょう。
ここではそれらの要素に触れつつ、LTVを向上させるポイントについて解説します。
購入頻度を増やす
購入頻度を増やすための施策は、いくつか存在します。
顧客との接触機会を増やし、購入のタイミングを計ってお目当ての商品やサービスを提案することはその1つです。DM配信やメルマガなど、プッシュ型の訴求手段が効果的です。
割引クーポンやポイントサービスは、既存顧客へのアプローチとしてよく使用されます。
LTVを上げるための施策では、アポイントから契約まで、WEB接客を使ったワンストップ対応によって、より高い成約率を達成できます。
また、CRMの導入によりお問い合わせ応対率が向上し、結果的にLTVが向上した例もあります。
購入単価を大きくする
購入単価を大きくすれば利益も増え、LTVも上昇します。顧客に買いたい、と思わせるような商品やサービスの魅力を訴求できれば、より高価なサービスを利用して貰えるでしょう。
新サービスを機に高額な商品への乗り換えを誘導する「アップセル」や、追加で関連商品を購入させる「クロスセル」も有効な手段です。
購入期間を長くする
購入期間を長くする施策には、次回購入時に特典を用意するのが有効です。ポイントの増量や、割引クーポンの提供はその代表例です。
アフターフォローやサポートを充実させて満足度を上げ、顧客にサービスの利用を継続したいと思わせることも有効です。要望に先回りしたり望まれた改善を反映させたりすると信頼感が醸成され、購入期間が延びます。
収益率を高くする
単価を上げると同時に、収益率を高くすると利益とLTVに直結します。
商品やサービスに要するコストを見直し、最適化することで収益率を高められます。メーカーとの取引や、人件費の見直しの検討も有効でしょう。
もちろん収益率が上がっても、商品やサービスの質を落としては本末転倒になります。費用対効果の見極めがポイントです。
顧客募集コスト・維持コストを下げる
LTVは、新規顧客の募集コストや維持コストにも相互に影響を与える指標です。
EC事業では、LTVによって顧客募集コストの上限を見極めるという考え方があることは先述しました。しかしLTVを過信して、短期間に新規顧客募集の施策を打てばバランスシートを割り込む危険性もあります。
既存顧客へのアプローチも、コストが負担になるレベルでは継続は難しいでしょう。
CPAで適切な広告費用を算出する
CPAとは「Cost Per Action」の略称で、顧客募集単価という意味です。
つまり、顧客を1人募集するためにかかる費用のことを指しています。
目標CPAとは、顧客募集にむけた広告やマーケティングにかける目標金額のことです。
算出方法は次の通りです。
LTVから目標CPAを算出すると、1件の顧客をいくらの費用で募集したいかを算出できます。また、1件あたりどの程度の利益を残したいかを決める指標にもなります。
CPA=広告費用÷コンバージョン数(募集した成果の数)
限界CPAの算出方法
限界CPAは、顧客募集のために使える広告やマーケティング費用の最大で利用可能な費用を算出する際に使うもので、「損失分岐点」とも呼ばれます。算出方法は、次の通りです。
限界CPA=顧客単価×利益率
広告費用が限界CPAまでに抑えられれば黒字、超えてしまった場合には損失が出ます。限界CPAをあらかじめ把握することで、さらなる黒字化への広告費用の調整や目標CPAの設定に役立つでしょう。
CRMでLTVを向上させる

CRMは顧客との関係性を情報化したものであり、顧客の行動や動向を分析するのに有用な施策です。そして、既存顧客との関係性の管理を通じてLTVとも深く関連します。
ここからは、CRMを活用してLTVを上昇させる方法について解説します。
CRMとは
CRMは、Customer Relationship Management(顧客関係管理)の略語です。既存の顧客情報を一元管理し、また情報を可視化することで顧客の行動や傾向を、効率的に分析できます。
CRMによる分析結果から既存顧客がいま求めているサービスを予想し、適切なアプローチをすることで顧客満足度や売上を上げられます。
問い合わせ内容やサービスの利用履歴のような個別の情報から、平均購入単価や平均購入頻度のような全体的なデータも分析できるため、LTVを上昇させるための施策に非常に相性のよい手法です。
CRMとLTVの親和性
CRMツールには顧客情報の管理や分析と、それをもとに施策を実施する機能が一般的に備えられています。データの分析結果に基づいて対策することで、売上やロイヤルティ(ユーザーのサービスに対する愛着度)の向上が期待できます。
既存顧客の維持に有用なだけではなく、顧客データからターゲット層を分析してこれまでより絞ったターゲティングをしたり、商品やサービスの改善点を見出したりといった効果も期待できます。
LTVはCRMが効果的に働いている指標でもあり、成果でもあります。
MAやチャットボットも有効
MAとはMarketing Automationの略語であり、マーケティング活動を自動化してくれるツールです。資料提供や会員登録時の返信メールに自動対応したり、入力情報を自動でデータに反映するなどの機能があります。
チャットボットは、顧客からの問い合わせに対し自動で応答するシステムです。近年はAI搭載型が主流となり、非常に精度が上がっています。顧客の疑問に素早く答えることでコンバージョン率を高め、かつ人的コストの削減にもつながります。
ともに、LTV向上に効果の高いサービスです。
LTV向上のためのマーケティング施策

LTVを向上させるための施策は、CRMだけではありません。EC事業という形態に特化した施策でも、複数の効果的な方法があります。
ここでは、LTVの向上を目的として効果が期待できる施策をご紹介します。
既存顧客の誘導
既存顧客の中には、サイトに登録したもののカゴ落ちなどで未購入の顧客も含まれます。そうした顧客を誘導することは見込み客を刈りとる施策であり、LTVの向上に対して即効性があるのです。
未購入の顧客に対しては、自動配信メールや誕生日インセントが適切です。対象商品が割引になったり付属サービスが追加されたりなどのタイミングは、顧客へのアプローチのチャンスといえます。
こうした施策を手動で運用するのは事務コストが大きいため、CRMツールを活用し自動化すると効果的です。
アップセルとクロスセル
より高額なサービスを訴求するアップセルと関連商品を推すクロスセルも、LTV向上に
効果があります。
具体的にはまとめ売りやセット売りによる購入単価のアップや、より高いグレードの商品の販売、あわせ買いなどで顧客の購入単価を引き上げる施策です。
セット売りでは、化粧品のセットなど同じカテゴリーの関連商品を組み合わせたり、購入商品と親和性の高い商品を訴求したりなどが有効でしょう。
同じリピート率でもより客単価があがるため、LTVが向上します。
休眠顧客復活の施策
休眠顧客とは、購入履歴があるものの長期間利用のない顧客のことです。こうした顧客へのアプローチは、LTVを向上させます。
具体的にはリマインドメールでセール情報やポイントの保有量を通知するなど、再購入のきっかけとなる情報をアナウンスします。
また、ECのLTVが下がる原因の多くは顧客満足度の低下にあるため、こうした休眠顧客の発生をできるだけ抑制して満足度を上げていく施策を心掛けることも、LTVを高く維持するために必要な施策です。
専門性の高い領域の事業であっても、案件に適した経験やノウハウが豊富な人材を配置することで、対応できる顧客を増やし、休眠顧客を減らすことへつなげられます。
顧客対応に、電話やメールだけでなくWeb会議システムでの対応を追加することで、より手厚い対応が可能となり、顧客満足度の向上にも役立ちます。
EC運営代行会社の活用
LTVを向上させるには、手間と時間がかかります。また、専門性の高い技術や経験が要求される場合もあるため、どうしてもLTVが上がらない場合はEC運営代行会社を活用することも視野に入れましょう。
大手通販サイトをチャネルにECを展開していた企業が価格競争に巻き込まれ売上が低迷しLTVが低下していた状態から、代行会社へのアウトソーシングで売上伸長に成功した例もあります。
効果的なアウトソーシングならば、プロの施策でEC事業を発展させて充分な費用対効果が得られる可能性があるのです。
▶ECサイトでの集客方法とは?自社商品の売上を上げる5つの施策を伝授!
LTVでEC事業を発展させよう

LTVはEC事業の運営における長期的な指標です。
LTVを向上させる施策は、ECの将来性を左右します。EC事業の活用のためのノウハウや経験が足りない場合は、運営代行などのアウトソーシングを選択するのも1つの手段です。
EC事業のアウトソーシングに興味のある方はぜひこちらをご覧ください。