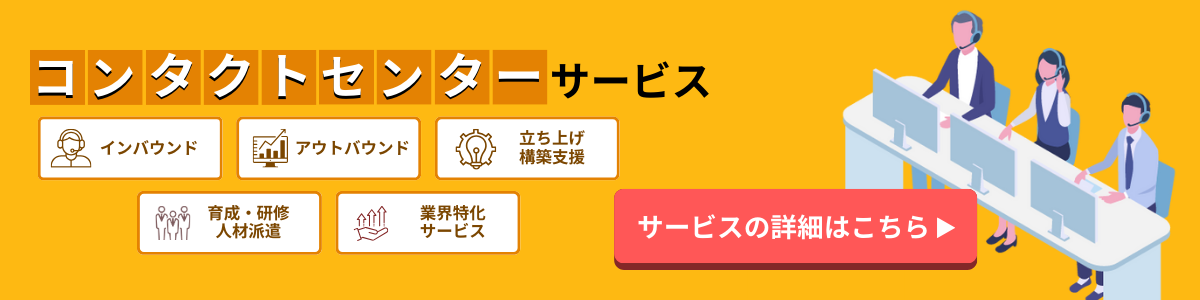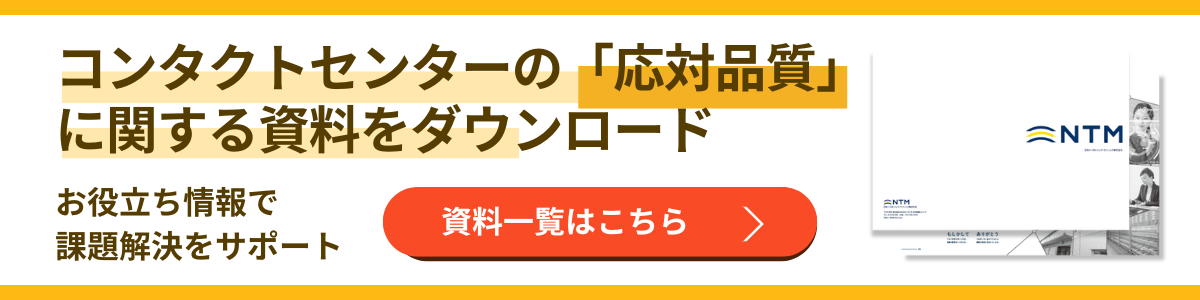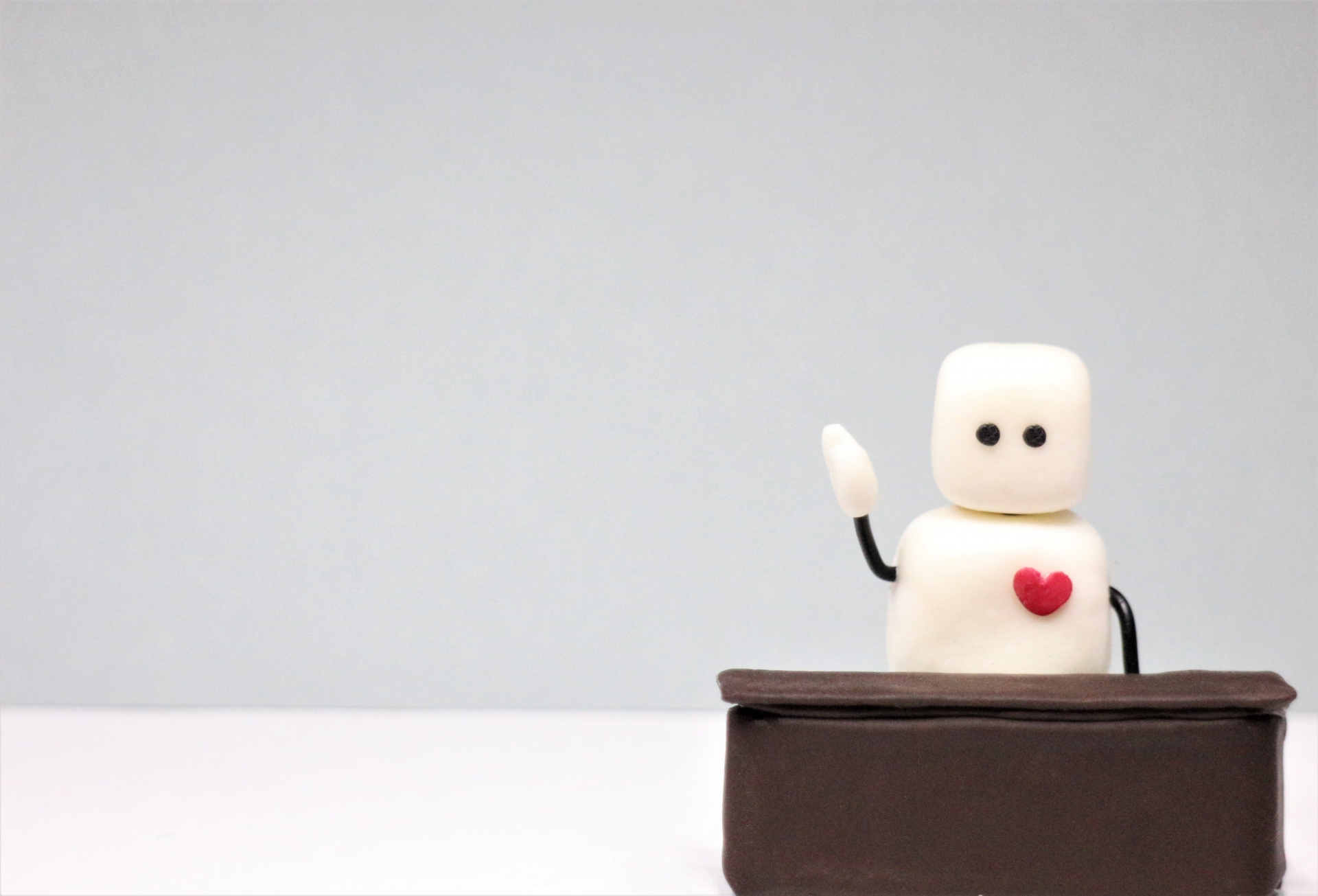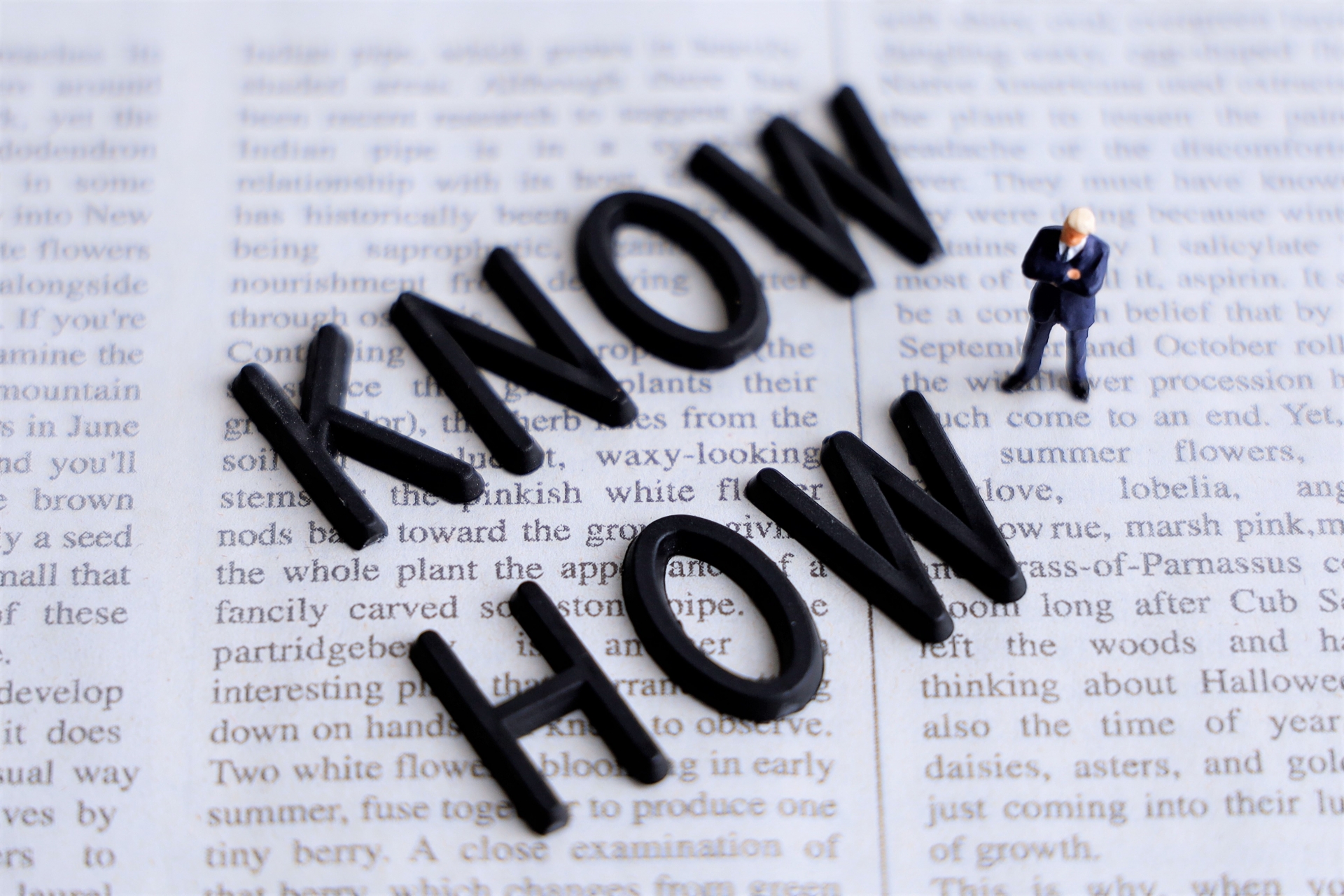コールセンターの品質管理とは?チェック項目や実践方法・ポイントを解説

コールセンター(コンタクトセンター)の品質管理は、顧客満足度や企業の信頼性に直結する重要な要素です。オペレーターの応対レベルや業務効率などの向上を図るためには、適切な品質管理が欠かせません。
しかし、「品質管理では何をチェックすればよいのか」「どのような方法で実践するのか」と悩まれている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、品質管理の基本から具体的な管理方法、取り組むポイントまで解説します。
目次
コールセンターにおける品質管理とは

コールセンターの品質管理とは、オペレーターの応対内容や業務のパフォーマンスなどを管理して、一定水準の維持または向上を図る取り組みです。
品質管理に取り組む目的としては、主に以下が挙げられます。
▼品質管理の目的
- 顧客満足度の向上
- 稼働率や業務効率の向上
- オペレーターのスキルアップ促進
品質管理を通じてオペレーターによる応対品質や業務スキルを向上させることにより、迅速かつ的確な顧客対応が可能になり、顧客満足度の向上につなげられます。
また、迅速な問題解決や待ち時間の削減によって稼働率が向上すると、限られたリソースで効率的な運用が可能になり、コールセンター全体の生産性向上にも貢献します。
コールセンターにおける品質管理の4項目

コールセンターの品質管理は、主に応対品質・接続品質・運営品質・処理品質の4つの項目に分類されます。それぞれの項目を適切に管理して総合的な品質の維持・向上を目指します。
➀応対品質(評価)
応対品質は、オペレーターによるコミュニケーションの質を指します。
評価ポイントは、「聞き取りやすい声のトーンや話し方」「スムーズかつ的確な回答」「課題・ニーズに対する問題解決能力」などであり、これらは、顧客満足度に直結する重要な項目となります。
応対品質が高いと顧客が安心して相談でき、企業に対して良好な印象を抱きます。
日本トータルテレマーケティング(NTM)のコンタクトセンターサービスでは、オペレーターによる電話対応およびメール・チャットでの対応の品質を、全社で統一した基準に基づいて評価しています。
電話対応の品質は、システムによる客観的な判定と、人による評価のハイブリッド方式で品質を評価・標準化しています。
例えば、システムでは判断が難しい電話での表現・イントネーション・説明のわかりやすさについては人の手で評価し、オペレーターにフィードバックすることで、継続的な品質向上につなげています。
②接続品質
接続品質は、コールセンターの窓口へのつながりやすさを指します。
顧客が電話をかけてからオペレーターにつながるまでの待ち時間や、呼損率(回線や設備の問題で接続できなかった割合)、放棄呼(顧客が途中で電話を切ってしまうこと)の件数などが評価されます。
顧客を待たせることなくスムーズに対応できる設備環境とオペレーター数を整備することが重要です。接続品質の向上により、顧客のストレス軽減と満足度向上を実現できます。
③運営品質
運営品質は、コンタクトセンターの運営体制や労働環境の質を評価する項目です。
適正な人員配置、業務プロセスの効率性、管理者によるフォロー体制、人材の育成体制などが主な評価ポイントとなります。運営品質を高めることで、オペレーターのパフォーマンスが向上して安定した品質でのサービスを提供できます。
また、働きやすい職場環境が整備されると、オペレーターのスキルアップ促進や人材の定着化などにつながることも期待されます。
④処理品質
処理品質は、顧客からの問い合わせや要望への対応のパフォーマンスの高さを示します。
一次解決率や平均処理時間、処理の正確性などの業務遂行スキルが評価されます。顧客の問題を迅速かつ正確に解決できる能力のほか、転送回数の削減や後処理時間の短縮も重要なポイントとなります。
処理品質の向上により、顧客満足度の向上とコールセンターの業務効率化を実現できます。オペレーターの業務遂行スキルに関係するため、継続的な教育が必要な項目といえます。
コールセンターにおける品質管理の重要性

コールセンターは、顧客と直接コミュニケーションをとる企業の「顔」となります。丁寧かつ的確な対応は顧客に安心感と信頼を与え、ブランドイメージ向上につながります。
また、単なる問い合わせへの回答ではなく、顧客の潜在的な課題・ニーズを汲み取って提案したり、多角的な視点から解決策を提案したりと期待を超える価値や感動を提供することで、顧客満足度の向上につながります。
このように品質管理を通じて顧客との信頼関係を構築することは、企業競争力を高めて持続的な成長を図るうえで重要と考えられます。社内での評価活動にとどまらず、経営戦略の一環として品質管理に取り組むことが大切です。
>>関連記事:カスタマーサポートの重要性 収益につなげる3つのポイントを解説
コールセンターの品質が低下する原因

コールセンターの品質が低下する背景には、さまざまな要因が複合的に関わっています。品質管理に取り組む際は、原因を特定して適切な対策を講じることが求められます。
問い合わせの急激な増加
新商品の発売やメディアへの露出など、外部要因による問い合わせや注文が急激に増えると、オペレーターの対応が追いつかなくなることがあります。
顧客を待たせる時間が長くなったり、丁寧な応対が困難になったりすると応対品質の低下を招きます。ピーク時の入電予測や適切な人員配置を行い、繁閑状況に応じたリソースを確保することが求められます。
オペレーターの能力不足
オペレーターの能力不足は、応対品質や処理品質の低下を招く原因となります。
例えば、「商材に対する十分な知識がない」「電話応対のトーンマナーができていない」「転送や保留などの基本的な操作にミスが起きやすい」などが挙げられます。
特に新人オペレーターの場合には、問い合わせに対する不明点が生じて対応に時間を要したり、誤った回答をしてしまったりすることがあります。個人のスキル習得をサポートするほか、基本的な応対フローや研修体制を整備するなどの仕組みが必要です。
システムの不具合
システムの不具合は接続品質の低下を招き、顧客満足度や稼働率に影響が及びます。
電話回線が不安定になったり、顧客管理システムの障害が頻繁に起きたりすると、スムーズな対応ができなくなります。このような技術的な問題を防ぐためには、定期的なメンテナンスとシステムの保守管理が欠かせません。
また、障害発生時に備えて迅速な復旧体制を整備することも重要です。
>>関連記事:コールセンターを自社で運営するには?起きやすい課題と対処法を解説
コールセンターにおける品質管理の方法

品質管理を行う際は、現状課題の調査から組織体制の整備、継続的な改善活動まで戦略的なアプローチが求められます。ここからは、一般的にコールセンターで行われる品質管理の取り組みを紹介します。
①調査
品質に関する調査を実施して現状課題を特定します。コールセンターの品質調査で行われる方法には、以下が挙げられます。
▼品質調査の方法
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| モニタリングスコア | オペレーターの通話内容をモニタリングして応対内容を評価する |
| ミステリーコール | 顧客を装って電話をかけてオペレーターの応対内容を評価する |
| 顧客アンケート | 通話後にメールやSMSなどでアンケートを送付して顧客満足度を調査する |
オペレーターの受け答えや業務遂行スキルなどに関する調査を通じて、客観的な評価結果をデータとして収集できます。また、コールセンターシステムや顧客管理システムなどから稼働状況や通話時間、コール処理数などを把握することが可能です。
②データ分析
調査によって収集したデータを基に具体的な課題と改善点を特定します。
応対品質・接続品質・運営品質・処理品質の各評価項目の結果を詳細に分析して、問題の根本原因を探ります。事前に設定したKPI(重要業績評価指標)と実績値を照らし合わせることで、目標達成度を定量的に評価できます。
また、時系列での変化やオペレーター間の差異なども分析することで、改善活動の優先順位を明確にして効果的な対策を検討できます。
③業務の改善
データ分析の結果に基づいて具体的な業務改善に取り組みます。
▼業務改善の取り組み例
- トークスクリプトの見直し
- 業務マニュアルの整備
- 管理者によるフォロー体制の見直し
- 働きやすい職場環境の整備 など
応対フローの標準化や業務体制の見直しなどを行うことで安定した品質のサービスの提供につながります。また、働きやすい業務環境を整備することにより、モチベーションやパフォーマンスの向上につながり、人材の定着においてもよい影響が期待できます。
④オペレーターの育成
応対品質に問題がある場合には、オペレーターの育成が必要です。
新人研修だけでなくスキルレベルに応じた定期的な研修を実施して、応用的な知識と技術の向上を図ります。個別のフィードバックを通じて各オペレーターの強みと課題を明確化して、能力や成長度合いに応じたスキルアップを支援することが重要です。
また、能力に応じた人事評価制度やキャリアアップの機会を導入することにより、オペレーターの自発的な成長を促します。
コールセンターにおける品質管理のポイント

コールセンターの品質管理に取り組む際は、客観的かつ定量的な評価とともに課題に応じた継続的な改善活動を行うことがポイントです。
品質管理の専任者を置く
コールセンターの管理者やSVは現場の管理に従事しており、品質の調査・評価・改善計画などに取り組むことが難しい場合があります。
専任者を置くことで、品質管理の実効性を確保して継続的・効率的な取り組みの推進が可能になります。また、コールセンター全体の品質基準を統一して公平性のある評価が可能になり、品質を保つことができます。
KPIを設定して管理する
品質管理に取り組む際は、評価の指標になるKPIを設定することが必要です。
例えば、「応答率を90%にする」「平均処理時間を30秒短縮する」といった具体的な数値目標を設定して、現状の数値が目標に達しているかどうかを確認します。
品質管理の活動によって得られた成果を定量的に把握することにより、別の改善策を検討したり、アプローチの方法を見直したりできます。
客観的な視点で評価する
品質管理を通じて顧客満足度の向上を図るためには、客観的な視点で「どのような品質基準を維持するべきか」を考えることが大切です。
例えば、応対品質を高めるために丁寧な対応を求め過ぎてしまい、通話時間が長くなることがあります。「顧客の課題を迅速に解決できるか」「ニーズに対して的確な提案ができるか」なども顧客にとって重要な評価項目になります。
フィードバックと改善を継続する
品質管理は継続して取り組むことが求められます。
定期的なモニタリングや顧客満足度の調査、社内のデータ分析などを実施して、フィードバックと改善策につなげることで高い品質基準を維持することが可能です。
オペレーターへのフィードバックについては、スキルの向上を図るだけでなく、成長の過程を評価することでモチベーションの向上にもつながります。
階層別の研修の実施
オペレーターの研修は、スキルに応じて階層別に実施することがポイントです。
新人オペレーターには、基礎的な応対マナーや商品の知識、ベテランオペレーターや管理職には応用的なコミュニケーションスキルやマネジメントスキルなど、それぞれの階層に合わせた研修が必要です。
外部研修には基礎・応用のスキルのほか、高齢者対応や医療・美容といった専門分野に特化したメニューを選択できるものもあり、自社の課題に合わせて活用することも有効な手段です。
コールセンターの品質管理は外部委託が可能

コールセンターの品質管理体制はすぐに整えられるものではありません。
ただし、こうした品質管理を外部に委託することができます。
オペレーターや業務プロセス、運営体制などの品質を評価して、現状課題の洗い出しや具体的な改善策の作成・実行などを依頼できます。専門的なノウハウによってコールセンターの顧客満足度やロイヤルティの向上、オペレーターのスキルアップを目指せます。
また、コールセンターの運営自体を委託できるサービスもあります。全社で統一した基準を設定し評価することで、安定した顧客対応を実現することができます。
>>関連記事:コールセンターの費用とは?外注と内製それぞれについて詳しく解説!
まとめ

コールセンターの品質管理は、オペレーターによる応対の質を一定に保ち、顧客満足度の向上を目指すために重要な取り組みです。品質管理に取り組む際は、客観的かつ定量的な評価を行い、課題に応じた継続的な改善活動を行うことがポイントです。
日本テレマーケティング(NTM)のコンタクトセンターでは、品質向上の仕組みとして「品質管理部」を設置しています。
オペレーターから管理者向けの研修に加え、化粧品などの専門分野に特化した研修など幅広いカリキュラムを整備しています。また、全件調査による品質維持や表彰制度・資格取得支援で意欲向上も図っています。さらに、ナレッジやシステムを活用した研修の一元管理、システムによるフィードバックの一元管理まで多面的な取り組みにより安定した品質とサービス向上を実現しています。
詳しくは以下の資料をご参照ください。